
文:小室敬幸(音楽ライター)

ヨーロッパの現代音楽の最新動向を追いかけているわけではない、日本のクラシック音楽ファンにとってパスカル・デュサパンといえば、「名前は聞いたことがある」とか「クセナキスの弟子」という程度の認識かもしれない。
きっと難解な音楽を書く作曲家なんだろうと思われているのだとしたら、その誤解だけでも解かせてほしい。もちろん、なかには難しさを感じる作品もあるが、基本的にデュサパンはエモーショナルな音楽を生み出す作曲家なのである。しかも近作になればなるほど、その傾向は顕著となる。 一例として、2017年にヴィクトリア・ムローヴァ夫妻によって初演されたヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲《スウィム・トゥー・バーズにて》の終わり3分半ほど(下記動画の23:55~)をお聴きいただこう。悩ましい妖しい響きが、透明感のある音楽へと昇華されてゆき、ヴァイオリンとチェロの美しい音色を堪能できる素晴らしい音楽だ。
いかにしてデュサパンは、このような音楽を書くようになったのか? かなり駆け足となるが、具体的な作品を挙げながら彼の足跡を辿ってみよう。
圧倒的な超絶技巧から、民族音楽風の旋律へ
デュサパンの初期作品で名高いのが、様々な弦楽器・管楽器のための無伴奏独奏曲である。特に重要なのがクラリネットとチェロで、作品を時系列で追うと特徴が掴みやすい。まずはクラリネットのための《イフ If》(1984)とバス・クラリネットのための《イトゥ Itou》(1985)を聴いてみよう。
同種の無伴奏曲といえばルチアーノ・ベリオのセクエンツァ・シリーズがあまりに有名。ベリオは1980年にクラリネットのための《セクエンツァIX》を作曲しているが、聴き比べてみれば分かるようにデュサパン作品の方が圧倒的に聴きやすい。クラリネットという楽器のもつテクニカルな可能性を充分に引き出し、なおかつ聴衆を飽きさせないようにメリハリのある音楽作りが徹底されているからであろう。加えて《イトゥ》では、裏返るような重音奏法の部分では具体的な音が定められておらず、奏者の裁量に任されるためフリージャズのアドリブのようなエネルギーが立ち昇る。
一方、1990年代以降のデュサパンは民族音楽から影響を受けるようになり、旋法的なメロディが作品の核となるケースが増えてゆく。クラリネットでは《イプソ Ipso》(1994)、チェロでは《イメール Immer》(1996)あたりの作品を聴けば、80年代の超絶技巧という要素はそのままに、架空の民族音楽を思わせる不思議な味わいが醸し出されていることが分かる。 そして21世紀になってから書かれた、チェロのための《イマーゴ Imago》(2001)を聴けば、更に旋律性が強まっていったことが、はっきりと理解できるはずだ。
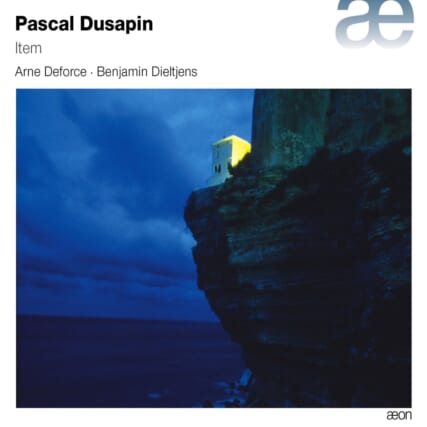
■デュサパン:器楽と室内楽作品集 Pascal Dusapin: Item (aeon/AECD1756)
アルン・デフォルス(チェロ) ベンヤミン・ディールティエンス(クラリネット)
デュサパン:アンシザ、イフ、アイテム、ラプス、代わりに、イプソ、イメール、オエ、イオタ、イマーゴ
名声を高めたオペラと、ドラマティックなオーケストレーション
デュサパンの音楽が旋律重視に傾いていったのは、1980年代後半からオペラに注力するようになったこととも関わりが深い。最初のオペラ『ロメオとジュリエット』(1985~88)の第6曲〈Après(After)〉を独立させた《レッド・ロック》は、語弊を恐れずにいえば、デュサパン作品のなかで最もキャッチーな楽曲だ。

■デュサパン:歌劇「ロメオとジュリエット」DUSAPIN: Roméo et Juliette (Accord-Una Corda)
ルカ・プファフ (指揮)
フランソワーズ・キュブレール (ソプラノ) ヴァレリー・ジョリー (メゾ・ソプラノ) ベルナデット・メルシエ (ソプラノ) ティモシー・グリーチェン (テノール) ニコラス・イシャーウッド (バス) オリヴィエ・カディオ (バス)
シリル・ゲルシュテンハーバー (ソプラノ) パスカル・ソジー (バリトン) ジュリアン・コンベー (バス・バリトン) アルマン・アングステア (クラリネット)
グループ・ヴォカール・ド・フランス
ミュルーズ交響楽団
2作目のオペラ『メディアマテリアル』(1991)は、なんとフィリップ・ヘレヴェッヘが指揮するバロックオーケストラのために書かれた作品。コロラトゥーラ・ソプラノが演じる王女メディア――ただし『ハムレットマシーン』で名高いハイナー・ミュラーの現代的翻案に基づく――の技巧的な歌唱を、声楽アンサンブルとオルガンとチェンバロと弦楽オーケストラという限られた音色で彩っている。彼女がいかに苦しみ、深く打ちひしがれているのかが、弦楽の響きによって強調されていく。
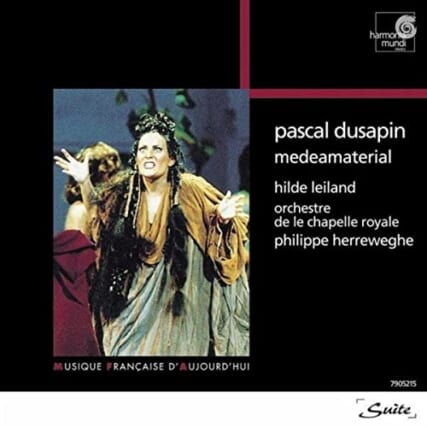
■デュサパン:歌劇「メディアマテリアル」DUSAPIN: Medeamaterial (harmonia mundi/HMC 905215)
フィリップ・ヘレヴェッヘ(指揮) ヒルデ・ライラント(ソプラノ)
コレギウム・ヴォカーレ・ヘント シャペル・ロワイヤル
生で聴けるデュサパン作品の魅力
こうしてデュサパン作品は時代を追うごとに、旋律性と情感を強めていったのである。今回、東京オペラシティで演奏される3つの作品にもこれらの特徴が当てはまるが、もちろんそれぞれの作品ごとに独自の魅力も放っている。
《エクステンソ》〜オーケストラのためのソロ第2番(1993~94)は冒頭で、分割されたヴァイオリン群が奏する「ド(C)」の音が、他の音へと「拡張(extension)」していく。弦楽器を主体とした叙情的なサウンドから徐々に管楽器の比重が増えてゆき、最終的には暴力的な金管楽器と打楽器の咆哮で「最大限(extenso)」のクライマックスを迎えるという作品。意外かもしれないが、おおまかなコンセプトは非常に分かりやすく、決して難解ではない。

■7つのオーケストラのためのソロ 7 Solos pour Orchestre (naïve/MO 782180)
パスカル・ロフェ(指揮) リエージュ・フィルハーモニー管弦楽団
弦楽四重奏曲第6番《ヒンターランド》(2008〜09)では、弦楽四重奏をソリストに設定することでオーケストラのサウンドを拡張。スティーヴ・ライヒの《ディファレント・トレインズ》の第2楽章(アウシュヴィッツを題材にした楽章)や、《トリプル・カルテット》(バルトークの弦楽四重奏曲第4番からインスパイアされた作品)のようなダークな情感を基調にしつつも、ミニマル的な規則的反復に縛られすぎない、多彩な音楽を聴かせる。

■デュサパン:弦楽四重奏曲第6番、第7番 DUSAPIN: String Quartets Nos.6 and 7 (aeon/AECD1753)
アルディッティ弦楽四重奏団
パスカル・ロフェ(指揮) フランス放送フィルハーモニー管弦楽団
チェロ協奏曲《アウトスケイプ》(2015)は、無伴奏チェロ独奏曲に傑作の多いデュサパンの面目躍如といえる作品。チェロとオーケストラが単に同じ音形を共有するというわけではなく、チェロをオーケストラがお互いを真似るプロセスを繰り返すことで、単純な対立でも融和でもない、新たな協奏曲の可能性を切り拓いている。
3作どれもがダイナミズムとリリシズムの両面を兼ね備えた傑作ばかり。21世紀のオーケストラ音楽を語る上でデュサパンは絶対に外せない存在になっていくはずだ。本人監修のもとで行われる演奏会は、日本ではまだまだ貴重なだけに絶対聴き逃がせない。
- 【特集】コンポージアム2021 featuring パスカル・デュサパン TOP
- フランス音楽界におけるパスカル・デュサパン・・・・平野貴俊(音楽学)
- デュサパン、人と音楽 〜友人からの視点で〜・・・・青木涼子(能声楽家)
- ぶらあぼ2021年5月号「コンポージアム2021」記事・・・・小室敬幸(音楽ライター)
- ゲネプロレポート・・・・小室敬幸(音楽ライター)

