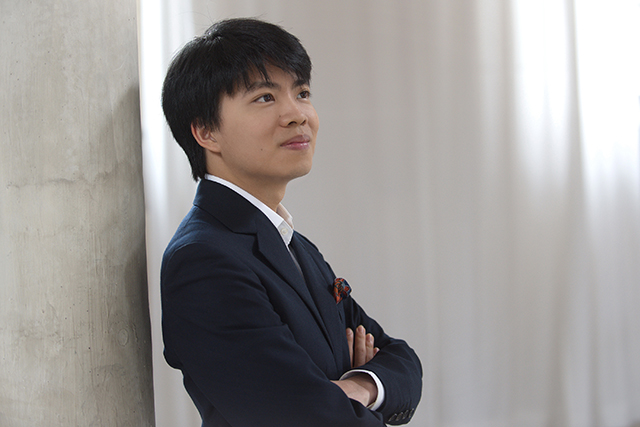文:青澤隆明

「ボクニワ ハジメト オワリガ アルンダ
コオシテ ナガイ アイダ ソラヲ ミテル」
やたらと暑い日の午後、思いがけず“Ballet Mécanique”が流れてきた。
曲がはじまってすぐ、メロディーを弾く手からして、天才のものだ。オルゴールを模すように弾かれ、少し弱気でシャイっぽくて、はねるところは可愛げにキュートで。
こんなふうに弾けるものなら、その心が聴き、その手が触れるところすべての音は、坂本龍一のメロディーになるのだろう。ここでは、音の身振りは、創り手にして弾き手である人の気の揺れや震えをそのまま伝えもする。
こんなにもフラジャイルで、脆い人間性を慈しむような手つきが、坂本龍一の音楽を歌っていたのだ。とても自信満々にはみえない、ひとつひとつの音を、心を籠めて弾いているひとりの男がいて、彼はその音楽を丹念に慈しんでいる。どうしてそんなことかできるかというと、それは彼がそのような天分の持ち主であるからだろう。
バーナード・ファウラーだったか、続いて聞こえてくるヴォーカルも儚げにやわらかく、どことなく所在なげで不安定だ。音程がずり下がっているようにも感じる。オルゴールやシロフォンのような音では少し跳ねている上行する旋律で、ふつうのヴォーカルなら張り上げるはずのところも、小さくスキップするようには弾まない。つまりはシャイに抑えられている。この歌が頼りなげに呟かれたかったからだろう。
おしまい近く、カタカナで記された詞が、機械的に主題を踊るときもそうだ。機械的であることは、ここではとてもフラジャイルに思える。ある種つくりものぽい素朴さや純情を歌う、直線的で規則的な旋律なのに、それが偽悪や欺瞞ではなく、照れや恥ずかしさのほうにキュートなカーヴを曲がっていることが、なぜか親しく胸に残るのである。矢野顕子が書いたという詩がまた実に素晴らしい。坂本龍一が素朴に歌うのにまさしくぴったりで。
機械がここで表現するのは効率性や功利性だけでなく、人間の脆弱さにおよんでいる。それは、機械を扱う手が、まさしくそうした繊細な手つきだからである。機械や電子を通じ反復されることで、それはなおさら記号化されるだけでなく、抑制された生々しさをもってくる。だから、その音楽はなにか特別な樹液のようなものになる。もっとエロティックに、蜜と言ってみてもいい。坂本龍一の音楽は、密やかに甘美な蜜を滴らせている。
バレエ・メカニークといえば、まずはもちろんジョージ・アンタイルである。これについては、シェイクスピア・アンド・カムパニーのことを書いた文でも少しだけ触れた。フェルナン・レジェとダドレイ・マーフィーの実験映画は、マン・レイの撮影もあってよく知られているし、私も美術館でみたことがある。そういうところだけをみると、坂本龍一の才能はかなりの部分が編集的な感性に導かれたものだということを、人がすぐにも言い出したくなるのはわかる。さまざまな好奇心に率直であるということは、その率直さにおいて才能なのである。編集という営みが組成であり創造であるなら、編集のない音楽はもちろんつくられない。つくるということは、それ自体で編集という意味を帯びているからだ。
それでも、いま私たちが思い出す坂本龍一の音楽には、あの、独特の身体性が不可分に宿っている。それこそが、その音楽のもつ心の性質であり動きだ。彼という人がそこに存在し、彼の手が触れて、音楽が発動したという、その身振りが直接であれ間接であれ、いや間接的にみえるときほど直接的にも感じられて、「ああ、私たちはいま坂本龍一の音楽に触れた」というふうに感じるのである。
坂本龍一の音楽を聴くとき、私たちはひとりひとりがそれぞれに坂本龍一という人間に出会っている気になるのだろう。減衰する響きの残像であれ、電子音響やメディアのなかを揺れて彷徨う亡霊のようなものであれ、そこには彼という人間が漠然と、しかし確実に存在している。それこそが彼という音楽家が、彼自身の音楽を生きていることの証しだろう。これが、私のずっと言いたかったことだ。
その独特に親密な感覚は、坂本龍一が楽器やコンピューターを扱うかぎり、紛れようもなく彼のかたちをしている。彼のかたちというのは、音の身振りであり、楽器や声部の重なりであり、なにより彼の耳がそれをずっと聴いているという実感によって確実に保証されている。
だから、自分はピアニストではないので、というふうに彼が口にするとき、それはピアニストのように上手には楽器を扱えない、というたんなる気後れだけではなく、彼はピアノとまったき同化はしておらず、ピアノが彼の器官の延長として自明の仕事を成しているのではないと、いうことを意味している。そのどこかに愛おしさと、名残り惜しさのような、メランコリーの感覚が滲んでいる。だから、坂本龍一のピアノは、ただピアノが弾かれているということを超えて、これほどまでに私たちに親しく聞こえてくるのだろう。
それは、いわゆる「作曲家のピアノ」であり、私たちがそう言うとき、それはたいてい20世紀的な意味で、プロフェッショナルなピアニストではないということを指す。職業ピアニストでないということ、つまりはアマチュアに留まるということは、彼が弾くのは言葉のよい意味で愛好家のピアノであるということだ。坂本龍一がピアノを弾くとき、彼はピアノを愛でている。できるだけ深く息を吹きかけるようにして、鍵盤に長くとどまるように、その指を伸ばしている。
彼の弾くピアノの音は、私たちにそのように触れる。技術で圧倒しようとか、パワーやエネルギーで制圧しようとか、完璧に近い構築で圧倒しようとか、もっと下品に言えば巧さで舌を巻かせようとか、かっこつけようとか、そういうことからは遠く離れて、きわめてパーソナルな体温をもっている。
だから、時代がパーソナルな快適さというイメージや幻想へと傾くとき、彼の音楽の湛える居心地のよさが、いわゆる癒しのように受けとられ、広い層の人々に伝っていったということも否定はできないだろう。しかし、その居心地のよさのような気分が、いつも坂本龍一という人がピアノを前にするときの居心地のわるさとそれをも含めた心地よさから率直に響いてきていたのは、とても重要なことだと思える。
坂本龍一のピアノはたとえ決然と意志を籠めても、どこかしら弱気に震えているように感じられる。ピアノという楽器がもつ透明で硬質な音、その響きの震動や減衰ということもまた、とりかえしのつかない愛惜のような情趣に親しい。それが耽美的に甘美さへと傾くとき、その心象には彼自身のナルシスティックな投影がみられるように聞こえてきたこともあったと思う。
それは、坂本龍一自身のナイーヴな率直さの表れで、それは彼がピアニストとしての武器という意味あいではピアノという楽器を操縦してはいなかった、ということの証左だ。正直に言えば、ある年代まで、彼の弾くピアノや、それを聴く人々の様子に、私は居心地のわるさを感じることもあった。
坂本龍一はあたかも観葉植物に水を与えるように自作を慈しむが、その姿勢そのものが、ピアノを弾くというパーソナルな表現行為を、ひとつのメッセージとして密やかに形象化していた。と書きながら思い出しているのは、「坂本龍一Playing the Piano 2009」のツアー終盤、川口総合文化センターリリアでのリサイタルを聴いていたときのことだ。
しかし、坂本龍一はおそらく、いつからかピアノと和解し、またピアノを弾く自分と和解し、さらにまっすぐ純粋にピアノを弾くことを楽しむようになった。2009年春のリサイタルからそう遠くない時節に、彼が弾く音楽の波紋が以前よりも、もっと素直に広がってくるように感じられた。
すると、聴き手がコンプレックスを感じる必要もなくなった。つまり私は自分自身のナルシシズムを感じることなく、彼がピアノで愛でる音楽に、抵抗や躊躇もなく、すっと入っていけるようになった。私自身もまた少し年をとり、少しだけ寛容になっただけかもしれないが、坂本のピアノもまたそのように、私にも寛容な響きをひらいてくれた、ということがあると思う。あるいは、彼とピアノ、音楽表現とピアノを弾く行為との間のずれが、包み込むような愛着からなんらかの屈折を解かれ、よい調和をとって、さらに心地よくひらかれたものになってきたのかもしれなかった。
ひとことで言うならば、ピアノを弾くことは触知的な探索であり、音楽を創ることは実験である。自らの感性や、愛する美を発見し認識していくための。それは個人的なものであり、個人が生きて聴きとってきた音楽の記憶としての営みだろう。さまざまに意匠やスタイルを変えながらも、あくまで音楽において正直であり、誠実であったということだ。坂本龍一の場合、それは自ずと自身の弱さに触れ、人類という種の脆さを映し出すものとなっていた。だから、これほど微細で、生命のつかない揺れが、水紋のように私たちの心に広がっているのだ。
それは、たとえば“Ballet Mécanique”がシンセサイザーで創られても、もっと言ってしまえば、藤倉大が手がけたオーケストラ編曲を、坂本龍一が指揮した東京フィルハーモニー交響楽団とのコンサートで生で聴いても、やはりまざまざと感じられた手つきなのである。つまり彼という人の手仕事は、楽器や演奏者の生理ということを超えて、曲の息づかいとして保たれるものなのだ。原曲を愛する巧みな編曲であれば。これを、作曲の天分と言わずして、なんと呼べばよいのだろう。決して、失われることのない手の感触。それは、しっかりとイメージされた音の質感と身振りだ。
「オンガク イツマデモ ツヅク オンガク
オドッテ イル ボクヲ キミハ ミテイル」
機をみるのに敏い人だったようにもみえるし、周囲や時代環境に流されることに素直だった人のようにもみえる。私には知る由もないし、結局のところ、誰も、彼自身でも知り得ないのかもしれない。しかし、彼がその内面においてどう動いていたかは、音楽のなかに現れているし、彼はあらゆることを彼自身の芸術表現としては音楽を通じて叶えようとしていたのだろう。
もともと逸脱を好んだ坂本の近年の音楽探求が、より「音楽」という概念から離れつつ、持ち前の好奇心でそれを拡張するように響きの世界、確認と認識の領域へと傾いていったのは、老いや病いという脆さを生の重要な側面として愛でようとする意志に寄り添うかたちであったのかもしれない。もちろん、それもまた時代の趨勢や地球環境の変化を鋭敏に察知してのものだったのかもしれない。後者における理論的な側面、いわば言語的なディスクールが、音楽家としての、もっと言えば人間としての直観をときに覆うようにみえてしまうとき、人々は彼の優秀な編集者としての才能をとかく称えがちになる。しかし、そうした思念が音楽に触れるのは、結局は彼の指を通じて、楽器を震わせる瞬間なのだ。音が波動の信号であることは、音楽であるだけでなく、人間であることの証しで、それは脳の電気信号の相似でもある、などとここでくり返す必要もないだろう。
もし坂本龍一をインスパイアし、あるいは彼が随所から借用してきたアイディアが、完全に外部からやってきたとして、それを音にするには彼の思索と心身の手が触れることが不可欠である。その意味で、坂本龍一はとても率直で、ナイーヴにすぎるほど素直で、純朴で、誠実だったようにみえる。そもそも、完全な外部というのものが、まったき内面というものと同じく成立するはずがないことは、それぞれが部や面という言葉で示されることからも明らかだ。内と外の境界に、音楽は生じる、少なくとも発生し、発声する。いま私たちが触れているのが、坂本龍一の内部なのか外部なのかはしれないが、それは彼の内面へと素直に誘い込む手のように、私には親しく感じられる。
そうして、いま坂本龍一のレコーディングを聴いている。それはもう、彼の手では決して鳴らされることのない音楽だ。その手つきは独特の生理をもっている。知性でどうこうする以前に、坂本龍一の天才はそこから直接に滲み出ている。それこそは、オンガクにほかならない。私たちが聴くのは坂本龍一の楽曲ではなく、坂本龍一という音楽なのだ。そう称えることが、彼の作編曲家としての仕事を軽視するものではないことは言うまでもない。
どれほどなにかに似ていても、誰かと交わって混じっているようにみえても、それは坂本龍一の音であり、彼の響きである。アルゴリズムで生み出されるようなものでは決してない。それは彼が上手に濁っていて、適切に澄んでいたことの証しだと思う。処世と天分はちゃんと折り合いがついていた。それはまぎれもなく、彼が音楽家として天才的に際立っていたことの証しだ。そう称えたところで、彼の創り続けた音楽を汚すことにはならないだろう。
そんなふうに、踊っている彼を、私はみていた。こうして、彼の音楽が広がる空を、いつまでもみている。人は踊り、風を起こし、微細に震える。空はずっと、そこにある。
「ボクニワ ハジメト オワリガ アルンダ
コオシテ ナガイ アイダ ソラヲ ミテル」
【Profile】
青澤隆明 あおさわ・たかあきら
音楽評論家。1970年東京生まれ、鎌倉に育つ。東京外国語大学英米語学科卒。主な著書に『現代のピアニスト30—アリアと変奏』(ちくま新書)、ヴァレリー・アファナシエフとの『ピアニストは語る』(講談社現代新書)、『ピアニストを生きる—清水和音の思想』(音楽之友社)。