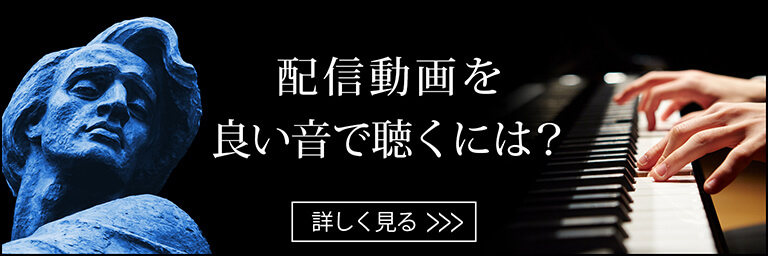これだからコンクールは面白い! 物議を醸してきた個性派審査員たちと審査の舞台裏
頂点を目指すピアニストたちの運命を大きく左右してきた、ショパン国際ピアノコンクールの採点。審査員には、このコンクールの過去の上位入賞者や世界的ピアニスト・指導者たちがズラリと顔を並べていますが、彼らの価値観もまた多様で、毎回激しい議論が交わされます。『ショパン・コンクール』(中公新書)の著者で、ご自身も多くのコンクールで審査に当たっているピアニストの青柳いづみこさん(今回もワルシャワ行きが決定!)に、これまでのショパン・コンクールの審査の裏側を解説していただきました。今年のコンクールでも、採点にまつわる新たな伝説が誕生するのでしょうか。

文:青柳いづみこ
ピアノのコンクールの審査は、よくフィギュアスケートの採点になぞらえられる。
以前は、テクニカル・メリットとアーティスティック・インプレッションの2項目に分かれ、それぞれ6点満点ずつで採点していたが、とくにアーティスティックのほうは文字通り「印象」なのでさまざまに割れ、不公平と思われる採点も少なくなかった。
そこで新システムに切り換えられたが、ヴィデオも使った詳細すぎる採点に、導入時には選手やコーチの悲鳴もきかれた。トリノ・オリンピックでの荒川選手の金メダルは、この新採点をいち早く取り入れた勝利でもあった。
しかるに、ショパン・コンクールはオリンピックではないのだから、当然のことながら細かすぎる採点方法は取り入れられていない(たとえば、Op.10-2やOp.25-6など最難曲の練習曲を見事に弾いた場合は加点されるなど、ありえなくはないと思うが)。

テクニックの差が歴然としていた時代はそちらの判定が前面に出ていた。それはそれで芸術面がないがしろにされる傾向にあったのだが、現在では教育システムが整備された結果、技術ではあまり差がつかず、解釈や選曲で差別化をはかるコンテスタントが多い。
最近では練習曲でもあまりスピードは出さず、内声を強調してみたり、響きを混ぜて思いがけない効果を出してみたり・・・解釈に凝る演奏が多いように思う。
過去のコンクールでもっとも物議をかもしたのは、1980年のポゴレリチのときだろう。圧倒的な実力をもちながら2次予選で敗退したのは、彼のマズルカに極端に低い点をつける審査員がいたからだ。このとき私の恩師、安川加壽子先生が審査員で、日本近代音楽館で閲覧した資料に全審査員の点数表がはいっていた。25点満点で採点し、優勝したダン・タイ・ソンは平均22点ぐらいだったが、ポゴレリチには2点とか3点しかつけない審査員もいたように記憶している。
解釈は多少変わっていても、すべての音を見事に弾いているのだから、この点数はありえない。アルゲリッチが怒って審査員を降りてしまったのもむべなるかなである。
このときは明らかに政治的な思惑が働いた結果だったが、数字的な思惑が働くこともある。2010年は3次予選から本選にいく過程で突然採点方法が変わり、審査員の小山実稚恵を困惑させた。当初は本選の採点をした上で予選からの点数を足して順位をつけるはずが、本選のみの評価で順位点をつけることになったのである。提案したのは2021年も審査員に呼ばれているケヴィン・ケナーで、私のインタビューに答えて、このままでは波のある弾き手に不利になると答え、例として3次予選まで不調だったヴンダーの名前を挙げていた。結果としては、もし合計点だったら上位入賞は望めないヴンダーが第2位となったが、本選のみ不調だったボジャノフは4位に後退した。結果を不服としたボジャノフは入賞者演奏会の出演をボイコットした。これでは賞金がはいらないから相当な覚悟だったことだろう。

2015年のコンクール、2018年のピリオド楽器のコンクールを視察して私が感じたのは、この情報化時代、コンテスタントの方が最近の動向に通じていて、YouTubeで過去の演奏も聴いている。審査員の知見が追いついていないのではないかということだ。
サッカーのワールド・カップでも審判の研修会は開かれるときく。ピアノの審査員も、どんな解釈が出てきてもそれが理論的に正しいか、単なるめちゃくちゃかを判断するための申し合わせが必要だろう。
興味深かったのは、古楽器とモダンの専門家が半数ずつ審査した2018年ピリオド楽器のコンクール。2位入賞した川口成彦によれば、審査員による公開講座の際、同じ譜面で解釈が真っ二つに分かれたという。バロックのスタイルでは左手と右手を微妙にずらすものだが、モダンの審査員はずれるのが嫌い。ところで、ジャン゠ジャック・エーゲルディンゲル『弟子から見たショパン』という本を読めば、ショパンがどのように弾いていたか一目瞭然のはずだが。
同書を読めば、ショパンが絶えず装飾を変えて弾き、生徒の譜面にもヴァリアントを書きつけたことがわかる。しかるに、2015年の予備予選で、ある出場者がオリジナルの装飾を加えて「ノクターン」を弾いたところ、審査員席はパニックに陥っていた。
ピリオド楽器のコンクールでは、第1次予選から楽譜にない装飾を加えたり、プレリューディング Preludng といって曲の前に即興的な走句を加えたり(1930年代までは慣例だった)、曲の間をアインガング Eingang でつなぐ演奏が相次ぎ、審査員の間で申し合わせが行われたという。
ショパンのように、ロマン派の時代に生まれながらリストやシューマンとは一線を画し、書法もスタイルも思想も18世紀バロックに近かった作曲家はひと筋縄ではいかない。
付点を入れるタイミングも装飾音のつけ方も、18世紀的に解釈するか19世紀寄りかで変わってくる。2015年のコンクールで入賞したあるピアニストは、妻がオペラ歌手であり、自分はショパンがカンティレーナに取り入れたベルカントのスタイルに精通していたが、それを理解しない審査員にじゅうぶん評価されなかったと不満をもらしていた。

もちろん、審査員たちはすぐれた音楽性と技術の持ち主で、多くが過去のショパンコンクールで優秀な成績をおさめてきた。門下からも優れた演奏家を輩出している。スタイルの違い、解釈の違いを乗り越えて本当にすばらしい演奏を聴きわける耳を持っているはずだとは思う。しかし、ここまで解釈が多様化してくると、なかなか対応がむずかしいのかもしれない、門下制による伝承式の教育に縛られているところもあるように思う。
今年のコンクールでは、2018年のピリオド楽器コンクールの成果は活かされるのだろうか。両方に出場するコンテスタントもいるようだが、プレリューディングやアインガングはつけ加えるのだろうか。それともモダンの審査員に配慮して「楽譜通り」弾くのだろうか。興味はつきない。

青柳いづみこ著『ショパン・コンクール – 最高峰の舞台を読み解く』(中公新書)
第18回ショパン国際ピアノコンクール 審査員
ドミトリ・アレクセーエフ Dmitri Alexeev
サ・チェン Sa Chen
ダン・タイ・ソン Thai Son Dang
海老彰子 Akiko Ebi
フィリップ・ジュジアーノ Philippe Giusiano
ネルソン・ゲルナー Nelson Goerner
アダム・ハラシェヴィチ Adam Harasiewicz
クシシュトフ・ヤブウォンスキ Krzysztof Jabłoński
ケヴィン・ケナー Kevin Kenner
アルトゥール・モレイラ・リマ Arthur Moreira Lima
ヤノシュ・オレイニチャク Janusz Olejniczak
ピオトル・パレチニ Piotr Paleczny
エヴァ・ポブウォツカ Ewa Pobłocka
カタジーナ・ポポヴァ゠ズィドロン Katarzyna Popowa-Zydroń
ジョン・リンク John Rink
ヴォイチェフ・シヴィタワ Wojciech Świtała
ディーナ・ヨッフェ Dina Yoffe
※ネルソン・フレイレ Nelson Freire、マルタ・アルゲリッチ Martha Argerichは辞退