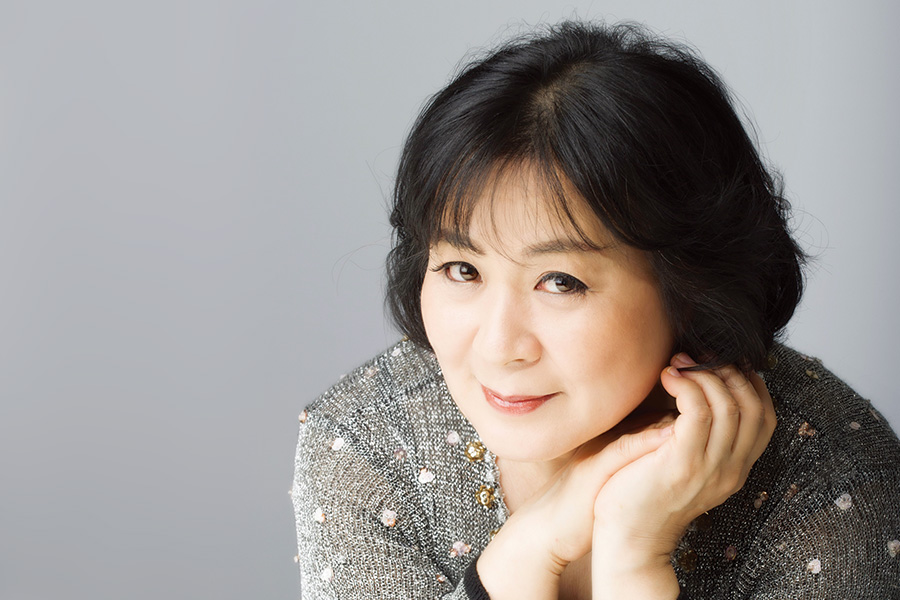取材・文:高坂はる香
(コンクール終了直後にワルシャワで行なったインタビューです)
── 長い審査、おつかれさまでした。
とくに最終審査の夜は長かったですね! 私はここで審査員を務めるのが4回目ですが、こんな状況は初めてです。6位までの入賞者が8人というのも初めてです。
最終審査は、ファイナルにまったく違うタイプが揃ってしまったために、決断を下すことが本当に難しくなってしまいました。別の方向の個性を持つピアニストが並んでいて、そのせいで、審査員がこれほど分断されたのだと思います。ある人はこれが好きで、ある人はまったく別のタイプが好き。今回は、普通ではありませんでした。
我々は、誰が完璧か、技術があり、プロフェッショナルで音楽的でショパンのスタイルを理解しているかを見ていくわけですが、あまりの個性に、それだけでは判断できなくなってしまいました。
でも優勝者については、マジョリティが選んだ結果、疑問が挟まれる余地なく決まりました。
── お弟子さんであるブルース・シャオユー・リウさんの優勝、おめでとうございます。彼の魅力は何でしょうか。
シャオユーと、もう一人の私の弟子で入賞したブイについて例えるなら、ブイは月で、シャオユーは太陽のよう。まったく別のタイプです。
シャオユーはダイナミックで、エネルギーと冒険心にあふれています。教師は普通、自分が望むほうに生徒を導こうとしがちですが、私は30年以上の教師と審査員の経験から、シャオユーには自由を与え、本質をそのまま伸ばしていくことにしました。
ですから、私がやったのは、彼が間違った角を曲がろうとしたら「それは違うよ」と指摘すること。まるでポリスのように(笑)。
── それで先生と弟子でも、あなたとシャオユーさんはまったくタイプが違うのですね。
そう、まったく違いますよね、エモーションの方向性が。シャオユーは輝かしい。どちらかというと、ブイのほうが私に近いかもしれません。教師としての最大のチャレンジは、自分のエゴや好みは忘れること。そして生徒の本質を一番に考え、自由を与えます。自由になることで、より印象的な音楽を奏でられるようになります。
── 確かにシャオユーさんの音楽は太陽のようで、優れた魅力的なピアニストです。同時に、ショパン・コンクールではショパンらしい演奏とは何かということが問題になりますが、その点についてはどうお考えですか。
これについては、時の流れにより変化していると思います。私がコンクールに参加した1980年は、これはショパンじゃないという議論がものすごく行われていました。だからこそ、ポゴレリチの審査についてのスキャンダルも起きたわけです。
でも時代は変わりました。ポーランド人の審査員ですら、とてもオープンになりました。インターネットのおかげで、さまざまな音楽の情報が得やすくなり、東洋と西洋のようなバリアを感じにくくなったのだと思います。昔は、アジアのピアニストにショパンを理解することは難しいと言われていましたが、今やそんなことはありません。好奇心と才能があれば、あらゆる情報が得られるのですから。
それによって、さまざまな種類のショパンの解釈に対して、私たち審査員も耳がデモクラティックになったのではないかと思います。
── シャオユーさんのマズルカをはじめとする舞曲は、とてもハッピーでリズムのセンスを感じるものでした。あなたは、マズルカはどう演奏されるべきだとお考えですか?
あはは! 最初にシャオユーがマズルカをもってきたときは、もっともっとハッピーだったんですよ。なので、ちょっと落ち着かせないといけませんでした(笑)。彼の演奏したOp.33は4曲からなりますが、いくつかはハッピーのままでいいけれど、いくつかはちょっと注意しないといけませんでしたね。
── マズルカを弾くには、スタイルの理解やリズムのセンスが必要なのかなと思いますが、いかがでしょう。
それについての答えは、イエスとノーですね。リズムのパターンはありますが、あまりにもそれに縛られすぎると、メカニックになってしまいます。とはいえ、リズムのパターンをまったく理解していないのも問題です。
ショパンはマズルカのリズムパターンをベースに、自分のスタイルを加え、インプロヴィゼーションやルバートを加えていきました。だからショパンのマズルカでは踊れないのです。マズルカは、タイミングに関しては最も自由でいいのです。
── 今回のファイナリストは、マジョリティが明るくハッピーな音楽性の持ち主だったように思います。本来ショパンの音楽は、哀しみや暗さ、笑っているのに涙が流れているみたいなものなのかなと思っていたのですが、今回は、ブライトでパワフルな音楽が評価されていたなと…それで、これはもしかして、今社会がそういう幸せな音楽を求めているということなのだろうか、などと思ったのですが。
そう、例えばシャオユーの音楽は輝かしい。私たち審査員の大部分も、聴いていてハッピーになれたり、喜びを感じられたりするものを求めていたのかもしれません。それはあなたが指摘する通りかもしれない。
その意味で、もしかすると従来の方法で作品の中に入っていって演奏したピアニストにとっては、残念ながら、結果が厳しいものであったかもしれません。私たちが参加していた時代は、人々がもっと深いものをありがたがっていたように思います。それに対して今は、より印象的で活発な音楽が評価されるようになった。ただ、もちろん限度というものがあり、それを越えてしまってはいけません。
このあたりは、プログラムの選択も重要だったでしょう。自分のキャラクターが明るいのならば、深くドラマティックな作品は選ばないほうが賢明です。
ショパンの音楽にはさまざまなキャラクターのものがあります。例えば若いショパンの作品には、ブリリアントでカラフルな作品も多い。一人の作曲家だけのコンクールは少ないですが、それが成り立つのは、ショパンのように幅広い作品があるからこそです。
── その他、入賞者やコンテスタントで印象に残っている方は?
今回、日本人は数と質、両方の意味で大きな成功をおさめましたね。これまで何度も審査をしてきた中で、最も印象的でした。すでにキャリアがある方もいましたし。昔は日本人っぽい演奏というのがありましたけれど、それぞれが学び成長して、個性がみんな異なるようになりました。喜ばしいことです。
まず入賞者の一人、小林愛実さんは、前回聴いているのと、コモ湖国際ピアノアカデミーでマスタークラスをすることもあったので、よく知っています。彼女のようにレベルの高いピアニストには、アドバイスをするにも、抽象的に雰囲気やムードを伝えるほうがいい。すると彼女はすぐにそれを吸収し、反映させるのです。
反田恭平さんは、今回初めて聴きました。緊張の影響か、ステージごとに波がありましたが、2次とコンチェルトは良かったですね。彼はとても経験のあるピアニストだということがわかりました。
あと、霧島国際音楽祭でお会いした進藤実優さんも知っています。大いに成長していたので、ファイナルに進めなかったことは残念です。日本人ばかり通すわけにはいかないという理由で落ちてしまったかもしれません。日本人は、5人もセミファイナルにいましたからね。
それから西洋の参加者でおもしろかったのは、ガルシア・ガルシアさん。ショパンの理解という意味では違うかなと思うところもありましたが、自分の音楽を持っていました。ある曲ではまるで天国にいるようなんだけれど、ある曲では苛立つくらい! ラウンドによって、すごく高得点だったり、通すことを迷うほどだったり。でも、とにかくポテンシャルを感じました。
今回は、音楽的にパーフェクトに演奏していて、ショパンらしく歌い詩的であるというだけでは十分でなく、加えて、この人は何を伝えようとしているのかがわかり、そこに十分なストーリーが感じられるピアニストが求められたように思います。あとは、すべての音、すべてのディテールに意識が届いているか、センスが感じられるかどうかも大切でした。
── そのショパンらしい演奏ということについて、コンクールを終えて、私は少し見失っているところがあるのです。コンクール前に審査員の先生方にお話を伺って、イメージを掴みかけていたような気がしていたのですが…。ショパンらしい演奏って、一体何なのでしょう!
あはは(笑)。日本では、正しいショパンの演奏というものをずいぶん気にする傾向があるようですね。昔、ポーランドでも『ショパンの正しい演奏法』というアカデミックな本が存在していましたけれど、それはもう過去のものです。今や、アカデミックに演奏しすぎて、自分のファンタジーやイマジネーションがないと、それは単なるスタンダードでしかありません。特にショパン・コンクールではみんなが同じ作品を弾きますから、スタンダードをやっても、群衆の中で違いを出すことができません。
そこで重要になるのがバランスです。ショパンのきちんとした理解のうえに、少しフレイバーを加え、フレッシュで個性的なものにする。工業製品のように同じ演奏ばかりでは、さすがの審査員も眠くなってしまいます。パーフェクトであることに加えて、パーソナルなタッチを持っていることが必要なのです。
── ショパンの理解も、多様性の時代に入ったということなのでしょうか。
そうでしょうね。デモクラティックというほうが近いと、私は思いますが。
♪ 高坂はる香 Haruka Kosaka ♪
大学院でインドのスラムの自立支援プロジェクトを研究。その後、2005年からピアノ専門誌の編集者として国内外でピアニストの取材を行なう。2011年よりフリーランスで活動。雑誌やCDブックレット、コンクール公式サイトやWeb媒体で記事を執筆。また、ポーランド、ロシア、アメリカなどで国際ピアノコンクールの現地取材を行い、ウェブサイトなどで現地レポートを配信している。
現在も定期的にインドを訪れ、西洋クラシック音楽とインドを結びつけたプロジェクトを計画中。
著書に「キンノヒマワリ ピアニスト中村紘子の記憶」(集英社刊)。
HP「ピアノの惑星ジャーナル」http://www.piano-planet.com/