
- 特集TOP
- ぶらあぼ5月号記事
- 特別対談:沼野雄司×小室敬幸|前編
- 特別対談:沼野雄司×小室敬幸|後編
- リハーサルレポート
- 武満徹作曲賞レポート
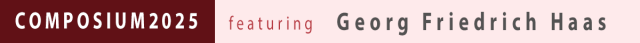
今年の「東京オペラシティの同時代音楽企画『コンポージアム』」は、オーストリア出身で現在はアメリカを拠点とするゲオルク・フリードリヒ・ハース Georg Friedrich Haas(1953〜 )をフィーチャー。自然倍音列から導き出されたハースの微分音の世界は、聴き手に新しい響きを体感させてくれます。彼の管弦楽作品2作を聴くことができる貴重な機会となる5月22日の公演を前に、音楽学者の沼野雄司さんと音楽ライターの小室敬幸さんが、ハースの音楽の面白さについてたっぷりと語り合いました。後編は、ハースの音楽と人物像をさらに深堀りします。
文・構成:小室敬幸
写真:編集部
小室 前半に続いて、もう少しハースのパーソナルな側面を掘り下げてさせてください。そもそも彼はかなり特殊な家庭で生まれ育ったようですね。
沼野 祖父母と両親がナチスの信奉者で、ハース自身は1953年生まれだから完全に戦後の世代なのに、日常的に暴力を受ける歪んだ環境で育ったというんです。その頃の自己分析を読むと、本当に知的な人だと分かります。
小室 2022年に出版されたハースの自叙伝『毒された時代を生きて:ナチ少年の回想録(Durch Vergiftete Zeiten: Memoiren eines Nazibuben)』に少し目を通してみたんですけど、読んでいて胸が苦しくなりました。その祖父母と両親からの虐待的な指導によって、ナチスは悪くないと教え込まれてしまい、学校の教師はみんな嘘を教えている!……と声をあげて反発していたのだと。それで友人もほとんどいなかったそうです。1974年、大学時代に「洗脳」が解けてからは罪悪感に苛まれ、心理療法を何年も受けたことでやっと、自分にとって「恥」ではあるけれど「罪」ではないんだと捉えられるようになったと語っています。真実に気付くきっかけをくれたひとりが作曲の師ゲスタ・ノイヴィルト(1937〜 )でした。

沼野 ゲスタは作曲家オルガ・ノイヴィルト(1968〜 )の伯父で、日本だとオルガの方が紹介される機会は多いんだけども……
小室 オルガはウィーン国立歌劇場の歴史上で初めてオペラが上演された女性の作曲家として2019年に話題になりましたし、サントリーホールのサマーフェスティバルで2023年に来日もしていますしね。
沼野 ゲスタ・ノイヴィルトはオルガやハースだけじゃなく、ペーター・アプリンガーも弟子だったし、エンノ・ポッペも一時期習っていた。他にもイザベル・ムンドリー、ベルンハルト・ラング、ハンス・ペーター・キブルツも輩出した名教師なんです。彼自身の作品もすごく良くて、ハースに繋がる要素もある。
小室 ハースはゲスタ・ノイヴィルトのあとに、フリードリヒ・チェルハ(1926〜2023/ベルク『ルル』の補筆者として著名)にも作曲を習っていますが……
沼野 ノイヴィルトの方がハースの音楽によっぽど近いと思います。
小室 直接指導を受けたゲスタ・ノイヴィルトのほかに、親たちからの「洗脳」から逃れるうえで助けになったのがケージ、シューベルト、シェーンベルク、チェルハ、リゲティ、ラッヘンマンの音楽だったそうで。
沼野 ケージの自由と偶然性に救われたという話は別のインタビューでも言ってましたね。それにシューベルトの名前が挙がるのは、分かる気がするなあ。ロマンティックな解釈を勝手にするならば、彼はナチ的な家庭のせいで自分の故郷オーストリアに良いイメージを持てず、だからどうしても、自分を受け止めてくれる、どこか架空の柔らかな世界としてシューベルトみたいなものが必要だった。実際、彼の作品ってあまり強烈な方向には進んでいかないですよね。おぼろげなノスタルジーが、不快な悪夢のように変化してゆく……という感じで。
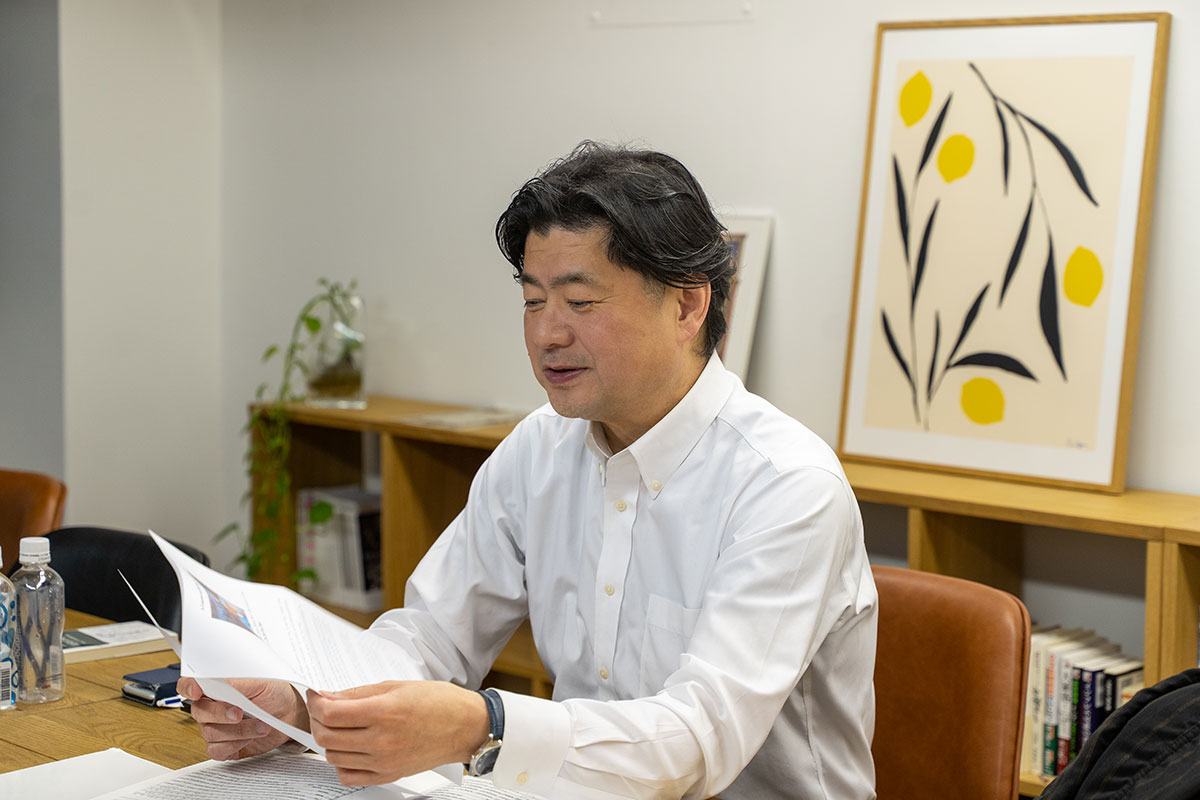
小室 シューベルトが未完成で遺したピアノ・ソナタに、ハースが個性的なオーケストレーションを施した《トルソー》(1999〜2000)という作品もありますが、ハースって作曲者自身が仕上げられなかった未完成作品に興味があるのか、他にもモーツァルトの《レクイエム》の補筆前の楽譜を元にした《7つの音空間》(2005)なんて楽曲もありますね。今回コンポージアムで演奏される《… e finisci già?》(2011)もそのひとつです。
沼野 しかもノスタルジックな曲ばっかり。
小室 ハースの弦楽四重奏曲第2番はハーゲン弦楽四重奏団のために作曲されたものなのですが、その解説で「伝統は何度も輝きを放つが、それは失われたもので、離れたもので、曇ったもののように見える」と書いているので、ノスタルジーを感じているのはおそらく間違いないですね。
沼野 ノスタルジーこそがハースの音楽の本質であるような気がします。
小室 でも、それが出来るようになったのも自分の苦しい生い立ちから、ある程度解放されたからなのでしょう。じゃなきゃ、いつまでも目を逸らしつづけてしまいそうですから。
沼野 ハースが抱えていた苦しみは他にもあって、それが彼の性的嗜好なんですよね。虐待されてきたからなのかどうなのか、妻となる女性に奴隷のようになってほしいという欲求がずっとあって。BDSM――B=ボンデージ、D=ディシプリンまたはドミネイション、S=サディズム、M=マゾヒズム――なんだと、現在はカミングアウトしていますね。

小室 サディスト的な嗜好はどうしたって親たちから受けたナチ的なものを連想させますよね。否定して我慢すべきというのは正論ですけど、消え去らずに欲求不満として自分のなかにあり続けたのが本当に辛かったんでしょう……。
沼野 同意の上で主従関係を結べる配偶者を得たことで、過去を清算しているじゃないかと僕は思うんです。やっと自由に、楽になったんじゃないかなあ。
小室 コンポージアムでメインプログラムに据えられている4本のアルプホルンとオーケストラのための《コンチェルト・グロッソ第1番 》(2014)は彼女と出会った翌年に初演された作品です。ハース本人たっての希望で、残りのプログラムは指揮を務めるストックハンマーと相談。「ファ#」が要所で核となる《コンチェルト・グロッソ第1番》と対を成す作品として、冒頭からヴァイオリン群が「ファ#」を伸ばしていくメンデルスゾーン:序曲《フィンガルの洞窟》を選んだとうかがいました。

沼野 こういう個展ではもっと新しい作品が選ばれることが多いじゃない? 10年以上前の作品をわざわざ挙げたということは、うまく仕上がった作品という手応えがすごくあったんでしょうね。4本のアルプホルンというのは、もちろんすごく変わってるんだけど、でもオーケストラは打楽器が多いだけの普通の編成です。新しい音響を模索している作曲家なのに。ベースはきっちりしていて、その上で変な音を出したいということなのでしょう。そしてアルプホルンはやっぱりノスタルジックな選択なのだと思います。
小室 最終的には、マーラー:交響曲第10番〜アダージョ、ハースの短めの作品《… e finisci già?》と組み合わせて4曲のプログラムになりましたけど、落ち着くまでにはドビュッシー、シベリウスなどの案もあったと事前にうかがいました。マーラー:交響曲第10番の主音も「ファ#」ですし、和声的な繋がりが重視されているのは間違いないですね。加えてマーラーのこの曲を選んだのは時間の「崩壊」――つまり決壊を迎える一点――にむかって変化していく音楽で、そこがハースと共通しているのだとストックハンマーさんは説明しています。今回はスタイルの全く異なる4曲をそうした観点で聴くのが面白そうです。
沼野 実際に鳴る響きとしては、マーラーよりもブルックナーに近い印象があるんですけどね。変な言い方だけど、シューベルトとブルックナーに通じるオーストリアの野暮ったさがハースにもありますよ。でも彼らのようなメロディはないので、響きの「触感」――触るほうだけではなく食べる方の「食感」も含めて楽しむような音楽なのかもしれません。
小室 前半でフランスのスペクトル楽派との違いについて話したときにも挙がりましたけど、ハースは「単純・単調になることを怖がっていない」し、「時間軸の論理的な構成はそこまで重要ではない」から、極端なことを言えば、作品によってはどこで終わっても良い音楽なんですよね。今回でいえば《… e finisci già?》がまさにそう。そう考えると未完成で遺された既存曲絡みの作品が多いのも納得というか。
沼野 ハースが自分を癒すための音楽であって、他者を癒やすことを目的としてないからなんだと思う。あと彼が審査員を務める武満徹作曲賞でどんな作品を評価するのかもすごく興味があります。

小室 本選に残らなかった応募者たちについて、ハースが「『私があなたたちの作品の価値を十分に評価できなかったのは私の問題であって、あなたたちの問題ではない。そのことに惑わされず、さらに発展を遂げてほしい』 却下されるのがどんな気持ちか、私はよくわかっている」とメッセージを綴っていたのがとても印象的でした。
沼野 敗者にも優しいんですね。彼の性格が滲み出てるなあ。
沼野雄司 Yuji Numano
東京藝術大学大学院博士課程修了。現在、桐朋学園大学教授。主に20世紀音楽をテーマに幅広く活動中。近著『トーキョー・シンコペーション 音楽表現の現在』(音楽之友社)では、新しい音楽批評のかたちを模索。他の著書に『現代音楽史 闘争しつづける芸術のゆくえ』(中公新書、第34回ミュージック・ペンクラブ賞)、『孤独な射手の肖像 エドガー・ヴァレーズとその時代』(春秋社、第29回吉田秀和賞)、『音楽学への招待』(春秋社)など。今年はイギリスの学会で日本の電子音楽について発表予定。
小室敬幸 Takayuki Komuro
茨城県筑西市出身。東京音楽大学付属高校および同大学・同大学院で作曲と音楽学を学んだ後、母校の助手と和洋女子大学の非常勤講師を経て、現在は音楽ライター。クラシック、現代音楽、ジャズ、映画音楽を中心に、演奏会やCDの曲目解説やインタビュー記事などを執筆し、現在は『音楽の友』『PEN』『ハーモニー』で連載をもっている。また現在進行形のジャズを紹介するMOOK『Jazz The New Chapter』に寄稿したり、TBSラジオ『アフター6ジャンクション』にも不定期で出演したりしている。共著に『聴かずぎらいのための吹奏楽入門』『ピアノへの旅』(ともにアルテスパブリッシング)。趣味は楽曲分析。
東京オペラシティの同時代音楽企画〈コンポージアム2025〉
ゲオルク・フリードリヒ・ハースを迎えて
ゲオルク・フリードリヒ・ハース トークセッション
2025.5/21(水)19:00 東京オペラシティ コンサートホール
出演/ゲオルク・フリードリヒ・ハース、沼野雄司(聞き手)
ゲオルク・フリードリヒ・ハースの音楽
5/22(木)19:00 東京オペラシティ コンサートホール
出演/ジョナサン・ストックハンマー(指揮)、ホルンロー・モダン・アルプホルン・カルテット、読売日本交響楽団
2025年度 武満徹作曲賞本選演奏会
審査員:ゲオルク・フリードリヒ・ハース
5/25(日)15:00 東京オペラシティ コンサートホール
出演/阿部加奈子(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
問:東京オペラシティチケットセンター 03-5353-9999
https://www.operacity.jp


