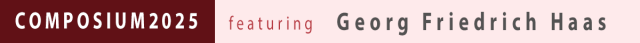
今年の東京オペラシティの同時代音楽企画〈コンポージアム2025〉では、オーストリア出身の作曲家、ゲオルク・フリードリヒ・ハースを特集します。作曲家本人が来日して、5月19日から川崎市麻生区にある読売日本交響楽団の黒川練習所でリハーサルが始まりました。翌20日に行われた2日目のリハーサル(この日はハースは不在)の模様を、音楽ライターの小室敬幸さんに速報でレポートしていただきました。

サー・サイモン・ラトルが「21世紀の主要作品」と評したゲオルク・フリードリヒ・ハースの代表作《in vain(無駄に)》(2000)が日本初演されたのは2015年のこと。それから10年間、ちょくちょくハース作品は日本でも紹介されてきているが、今年の「〈コンポージアム2025〉ゲオルク・フリードリヒ・ハースの音楽」は絶対に聴き逃がせない。何故なら作曲者本人がお気に入りの一作《コンチェルト・グロッソ第1番》(2014)が日本初演されるのだが、バーゼルで結成されたホルンロー・モダン・アルプホルン・カルテットのために当て書きされた「4本のアルプホルンとオーケストラのための」作品なので、彼らを呼ばない限りは日本国内での再演が事実上不可能だからだ。今週の木曜日(5月22日 19時開演)を逃すと、もしかすると日本では二度と聴けないかもしれない。

(写真は5月21日東京オペラシティ コンサートホール)★
ホルンロー・モダン・アルプホルン・カルテットと共に演奏を担う読売日本交響楽団のリハーサルを5月20日に取材した。読響は2018年に前音楽監督であるカンブルランの指揮で、ハースの管弦楽曲《静物》(2003/※カンブルランが世界初演)を取り上げているとはいえ、半音よりも狭い微分音を用いた繊細な響きを特徴とするハース作品は常に著しく演奏が困難。作曲者から厚い信頼を得ている指揮者ジョナサン・ストックハンマーは、どのように読響を導いていくのだろうか?
*****
ハースの世界へといざなう20世紀音楽としてのマーラー
見学した2日目のリハーサルでは、メンデルスゾーン以外の練習が行われた。まずは前半にプログラミングされたマーラーの交響曲第10番 嬰ヘ長調の「アダージョ」。よく知られているように、この曲はマーラー自身がオーケストラのスコアまでしっかりと書き上げたのは第1楽章のアダージョのみなので、現在のように補筆完成版が広く認められるまでは「アダージョ」だけを演奏するのが当たり前だった。プログラミングされた理由は、ハースの《コンチェルト・グロッソ第1番》では「ファ#(嬰ヘ)」が主音のような役割を果たすので、“嬰ヘ”長調の「アダージョ」との繋がりを狙っているのだという。

どうやら話を聞けば、前日のリハーサルで楽器の配置が大きく変更されたらしい。第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが左右に分かれる「対向配置」で、なおかつコントラバスが最後列で横一列に並ぶ「ウィーン式」の配置がとられた。それでいて指揮のストックハンマーがこの曲を、19世紀末の延長線としてではなく、20世紀音楽として捉えているのは明白。決して粘っこくはならないが、それでいてブーレーズほど淡白でもない。楽譜に書かれた指示を丁寧に拾い上げていった結果、純粋な音響体としての独創性が際立っていく。
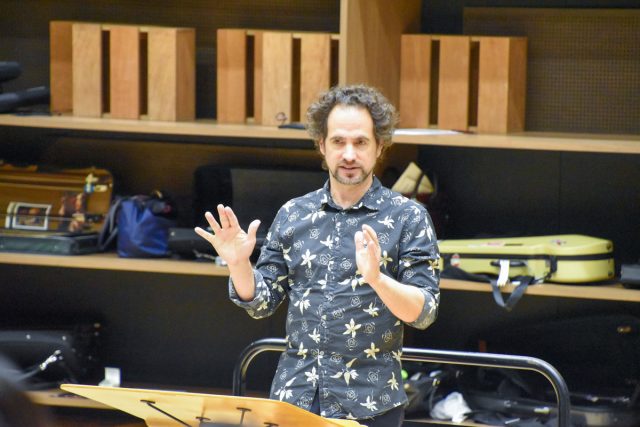
意外だが最も印象的だったのは破局的な不協和音が鳴り響くクライマックスのあとに回帰する「嬰ヘ長調」の滋味深さ。本番では休憩を挟んで次に演奏されるハースの《… e finisci già?》でも溜め込んだ鬱憤を吐き出すかのようなカタルシスを迎えたあと、ニ長調の響きがとろけるほどの美しさに感じられるのと非常に似通っているのだ。対向配置であることも存分に活かされており、本番でも音響の立体感が堪能できるに違いない。

*****
これぞ微分音音楽の真骨頂! アルプホルンが生み出すうなり
いよいよリハーサルの2曲目は《コンチェルト・グロッソ第1番》。前半はアルプホルン奏者が見守りに徹し、オーケストラだけで細部をつめていく。まずは演奏するたびにテンポを柔軟に変更する必要がある部分から練習がはじまった。どういうことかといえば、2つの音が鳴ったとき、全く同じ周波数だと完全に調和するのだが、少しでもずれるとヴィブラートのような“うなり”が発生する(いわゆる不協和音とは違うもの)。この“うなり”の周期にあわせて打楽器が刻むパルスが、新しいテンポとなっていく……というつくりになっているのだ!(アルプホルンには手で操作するピストンやバルブは付いていないので、ナチュラルトランペットのように唇の感覚だけで音の高さを変えていく。だから演奏のたびに“うなり”の速さが結構変わってしまう)。こうすることで自然な音の物理現象から有機的に音楽が生まれていくかのような印象を観客にもたらしてくれるのが面白い。

そして微分音の演奏も想像を超える難しさだった。この作品の冒頭ではコントラバス以外の弦楽器全員が分奏になり、38パートが少しずつずれるように音の高さもリズムも演奏しなければならない。少しずつずれるとはいえ、他の奏者を聴いてからでは当然間に合わず、自分だけを頼りにして演奏し慣れない微分音を正確に演奏しなければならないのだ……。ストックハンマーは時おりノートパソコンやスマートフォンを持ち出し、いま必要な微分音を鳴らして、丁寧にハースが求める響きをオーケストラへと伝えていく。

こうした下ごしらえの後、4名のアルプホルン奏者が加わった。そもそもコンチェルト・グロッソというのはバロック時代に誕生したスタイルで、小さな編成だけの演奏と(その小さな編成を含んだ全員による)大きな編成の演奏を対比させながら音楽を進めていく……というのが基本的な考え方。確かにこの曲でも、アルプホルンの演奏する純正律的な「倍音列」と、オーケストラの平均律的な「十二音調律」が対比されているのだが、聴いていて強く印象に残るのはこの2つの世界が混じり合い、時に調和、時に侵食しあうところではなかろうか?

指揮者ストックハンマーが語るハースの音楽
実は、指揮のストックハンマーはある程度日本語が話せるため、ハースの音楽を演奏する上で一番大事なのは「鳥肌」が立つことなんだと日本語でオーケストラに語りかけていた。リハーサル後にその真意を詳しくうかがったところ、こう答えてくれた(回答は英語)。
演奏しているときに何が助けになるか、何が必要ないかを考えながら、ミュージシャンたちにはなるべくシンプルに説明するようにしています。彼らがリラックスして気分が良ければ、音楽が難しくても結局は問題ないからです。しかし緊張していると良い音は出ません。だからミュージシャンたちにとって「鳥肌」がたつ瞬間を見つけたいのです。彼らが喜び、気持ちの良い瞬間を見つけられたのなら、そのために戦ってくれるでしょう。
私がこのことに気付くきっかけとなったのは、初めてコンサートでハースの《in vain》を聴いた時でした。この曲は途中から会場が暗闇になったり、光がついたりするのですが、そのなかでゆっくりとトロンボーンが演奏する部分を聴いて私は「鳥肌」が立ったのです。その瞬間を「トロンボーン・サンライズ」と私は勝手に名付けました。ドリンクの名前みたいでしょう?(笑)。その瞬間を経験してからハースの《in vain》が大好きになったんです。自分が指揮する時にはミュージシャンにも伝えると、何か繋がりをもって演奏してくれるようになりました。そうすると観客も繋がりを感じやすくなり、とても理解しやすいことに気付いたんです。これが私のトリック(秘訣)なんですよ(笑)。

加えて、指揮者の立場から代表作《in vain》(2000)と今回演奏される《コンチェルト・グロッソ第1番》(2014)では何が違うのか? ハース作品にどんな変化が起きていると思うかも尋ねた。
《in vain》は「意味がない」「無駄」といった意味で、物事がうまくいかない状態をいいます。音楽面からいえば、「純正律」と「平均律」が一緒に存在できないということを意味しています。もうひとつ重要なのは、この曲が〔ハースの母国である〕オーストリアの政治が非常に右側に傾いた時期に書かれた作品だということです。進んでも進んでも到着できない。それを《in vain》とハースは言っているのです〔※訳注:最初の部分が最後に回帰する構造になっている〕。
ところが多くの美しい瞬間がある《コンチェルト・グロッソ第1番》は違います。そもそも到着しようとしていないのです! この曲では、互いに聴き合い、共有し、コミュニケーションをとることが大事にされているように思います。そして複数の純正律が用いられているというのも重要ですね。アルプホルンは基音の異なる複数の楽器を持ち替えます。「ファ#」の倍音列に基づく純正律の響きは宇宙全体のように感じられ、完璧な調和が成り立っています。でも「ソ」の倍音列もまたひとつの宇宙であり、完璧なものなのです。どちらかを選び取る必要はなく、別の完璧さに誘惑されて往復する……それが《コンチェルト・グロッソ第1番》で起きていることです。

つまり《in vain》が社会への諦念だとすれば、希望を掲げているのが《コンチェルト・グロッソ第1番》ということになるだろう。まるで村上春樹が「デタッチメント」から「コミットメント」へとそのスタンスを変えていったような変化が、ハースにもあったのかもしれない。また現在のハースにとって《in vain》のような作品ではなく、《コンチェルト・グロッソ第1番》のような作品を大事にしている理由も視えてきた。
*****
倍音列が積み重ねられた美しい響きに身を委ねる
リハーサルの3曲目は《… e finisci già?》(2011)で、これも《コンチェルト・グロッソ第1番》に通じる明るい希望が感じられる作品だ。編成が三管編成から二管編成へと小さくなり(コントラバスに至っては8本から2本に減る)、モーツァルト時代のオーケストラの規模となる。この曲は構成が非常に分かりやすく、ハース入門にうってつけの作品となりそうだ。

倍音列が最終的に第24倍音まで重なっていく第1部(ただし低音から積み上げていくわけではないのが面白い)、倍音の響きを変奏していく第2部、そしてモーツァルトのホルン協奏曲第1番 第2楽章ロンドから素材がとられた第3部……という流れ。特に第3部はまるでブライアン・イーノのアンビエント・ミュージックを聴いているかのような美しさ!(名曲《パッヘルベルのカノンに基づく3つの変奏曲》を思い起こさずにはいられない)。ストックハンマーの導きで丁寧に美しい響きへと整えられていくと、まさに「鳥肌」が立ってしまう。演奏はやはり難しいが、聴く上での難解さは皆無といっていいほど。生演奏でしか体験できない官能的ともいえる倍音列に基づく響きの海に身を委ねよう。これは絶対に聴き逃がせない!
取材・文:小室敬幸

★印=撮影・写真提供:東京オペラシティ文化財団
無印=写真:編集部
東京オペラシティの同時代音楽企画〈コンポージアム2025〉
ゲオルク・フリードリヒ・ハースを迎えて
ゲオルク・フリードリヒ・ハース トークセッション
2025.5/21(水)19:00 東京オペラシティ コンサートホール
出演/ゲオルク・フリードリヒ・ハース、沼野雄司(聞き手)
ゲオルク・フリードリヒ・ハースの音楽
5/22(木)19:00 東京オペラシティ コンサートホール
出演/ジョナサン・ストックハンマー(指揮)、ホルンロー・モダン・アルプホルン・カルテット、読売日本交響楽団
2025年度 武満徹作曲賞本選演奏会
審査員:ゲオルク・フリードリヒ・ハース
5/25(日)15:00 東京オペラシティ コンサートホール
出演/阿部加奈子(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
問:東京オペラシティチケットセンター03-5353-9999
https://www.operacity.jp




