時代とともに歩んだ80年の軌跡をたどる

池辺晋一郎は、「時代を映し出す鏡」のような作曲家である。
1943年生まれ、60年代の安保闘争の頃に学生時代を送った世代。社会で起きている出来事のすべてに対して、常に鋭敏であり続けてきたし、そこに個人がどう関わるのかという問いを作品の中で発し続けてきた。
音楽のみならず言葉の人でもある。池辺さんと話していると、中原中也や立原道造などたくさんの詩人たちの言葉が、幾らでもすらすらと口をついて出てくる。詩とともに生きている人なのだ。映画『楢山節考』やNHK大河ドラマ『黄金の日日』をはじめ、映画やテレビや演劇とも長期間にわたり密接に結びついてきたことも重要である。たとえ器楽曲であっても、映像やドラマの雰囲気が池辺さんの曲にはどこか漂っており、そこが大きな魅力ともいえる。
影響を受けた武満徹についてはこう語る。
「たとえば武満さんのある一つの曲を聴いたときに、これは武満さんがどうしてもこのような音楽に結実させるしかなかったのかというと、そうじゃないっていう感じがするんです。茫漠とした“ゆとり”みたいなものがある。その周りの“ゆとり”のところには、詩があるかもしれないし、絵画があるかもしれない。いろんな全部のものが周りを覆っている。その中のたまたま音楽という要素を僕らは今受け取ってるんだという感じがいつもする。それが武満さんのあり方だと思う。
僕はアシスタントをしていましたけれど、作風とか作曲技法の上で武満さんにアプローチをしようと思ったことはないんです。けれども、そういう作り手としてのあり方というか、座り位置みたいなものは、武満さんは素晴らしいなといつも思っていて、ああいう風にありたいなと思っています。
武満さんの言ったことで一番好きなのは、『何ほどのこともなく作曲していたい』って言葉なんです。僕もそうやってきたなと思う。他のことをいろいろやってる中で一つ、作曲ということもやってるんだという風なアプローチで作曲をしていたい」
作曲だけの専門家ではなく、より総合的な人間の営みの一環としての音楽。とても美しい考え方である。
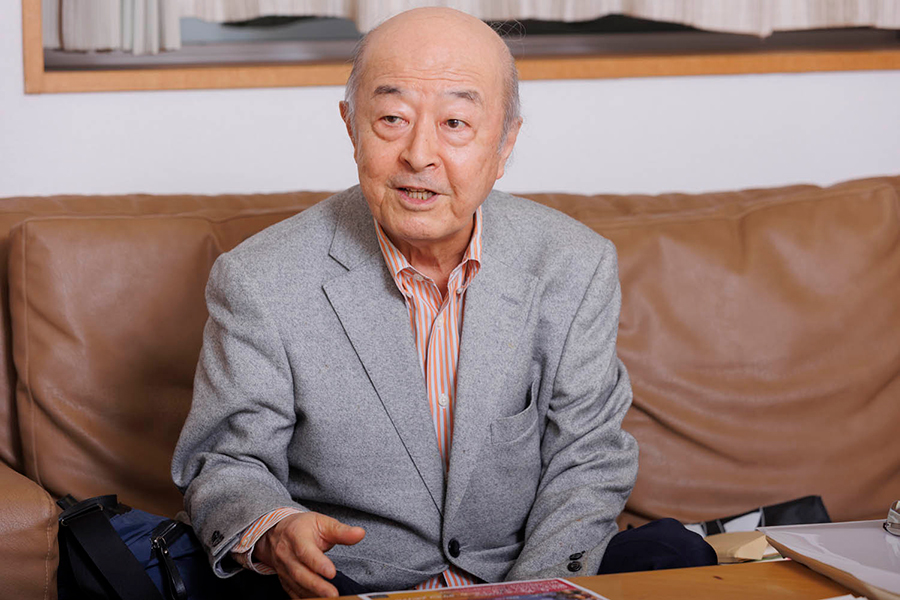
ところで、池辺さんは独自の形式や作曲技法についてのこだわりはあるのだろうか。
「若い頃はありましたが、ある時期からそういう技法的なことはほとんど考えなくなりました…というよりも、自分の頭の中にある音を定着させる、ということしか考えなくなりました。自分の方法論を持つというのは意識して避けましたね。
例えば、僕の友人なんかでもそういうのはあるわけです。自分のやり方っていうのがあって、それを持っちゃうとですね、例えば創作というものが100で完結するとすると、そのうちの30の地点からいつでも始めるみたいになるわけです。はじめの30はもう基本的に自分の技法として決まっている。それがとても嫌だったですね。僕はいちいちゼロから始めたい。だから、この曲ではどういう技法で行くっていうその技法のことは考えないで、ゼロから自分の中でどういうものが浮かぶか?どういうものが沸き起こるか?というところに自分の書き方を託したい。そうじゃないと面白くなくなっちゃったんですよね。
僕の師匠のひとり、三善晃さんが『ちょっと十二音技法をやってみようと思ったら、つまらなかった』と言っていたことがあります。『ある程度方法論が決まっていてつまらない』と。それと近いかもしれません。このシステム上、次はこの音だっていうのが決まっていたら嫌なんですよ。自分でそれは決めたい。そういう何かの技法で出発して、例えば100のうちの30から出発するっていうのは、だいぶ前に、40歳頃からもうやらないって自分で決めましたね」
池辺さんの“方法論を持つことを意識して避ける”という考え方は、いわゆる現代音楽に対して私たちが抱きがちなイメージとは大きく異なる。「このような技法を使う作曲家である」というような定義の仕方じたいが、もはや貧困なのではないかという気さえしてくる。ともあれ、常にゼロから出発するというのは、圧倒的に「書ける」作曲家だからこその自信なのではないだろうか。
いまの作曲家たちの中では、過去のクラシック音楽を幅広く知り、吸収し、さまざまなコンサートやオペラに足繁く通い、演奏に耳を傾け続けてきたことも池辺さんの特徴だろう。いわゆる現代音楽という小さな世界だけの住人では決してあり得ない。
「もちろん、新しいものを生み出したいわけですよ。新しいものを生み出すには、新しいって何か?を知らなきゃならないし、新しいものを知るということは、過去に何があったかを知ることです。そういう論理にたどり着くと、今までにあったものへの興味が出てくるわけですよ。
やっぱり元々は好きなわけですからね。現代音楽をやっているからロマン派のものは聴かないとか、そういう方が僕はよくわからないですね」

東京オペラシティ コンサートホールの楽屋での今回のインタビューで、おもむろに池辺さんはピアノの前に座り、自身にとっての道しるべのような作曲家としてシューマンやドビュッシーの一節をさらりと弾きながら、いかにも愉快そうに分析してみせた。過去の音楽も、たっぷりと身体の中に入っているのだ。
いよいよ9月15日には東京オペラシティ コンサートホールで「池辺晋一郎80歳バースデー・コンサート」がおこなわれる。そこで特に注目されるのは、交響曲第11番「影を深くする忘却」(東京オペラシティ文化財団とオーケストラ・アンサンブル金沢による共同委嘱)の世界初演だろう。
いまの作曲家には、交響曲を創作活動の根幹としている人と、全くこの形式に関心を払わない人がいるが、池辺さんの場合は前者にあたる。
「例え委嘱であっても、自分でほとんどゼロに近い地点から構想を練って書ける場合に書きたいのが交響曲なんですよ。これまでの僕の交響曲はすべてそういう形ですね。つまり交響曲とは、僕が自由に発想した曲ですよという宣言でもある。ある程度長さがあったとしても、委嘱者から内容について具体的な提示があったりしたときは交響曲とは名付けません。そういう呪縛からすっかり逃れて自分の好きにできるときに、交響曲へと結実する」

第11番のタイトル「影を深くする忘却」は、長田弘の詩『森のなかの出来事』の一節だが、そこにはさまざまな意味が込められている。例えば、震災と原発事故のこともつい思い浮かべてしまう——。
「忘却ということを考えなきゃいけない時期になってきたということですよね、人間は忘れる動物でもあるし、忘れるっていうことはある意味では価値があるし、忘れるからこそ次があるんだけども、何もかも同じ価値でそうやって過ぎ去っていっていいのかどうか。もうちょっとスパンを長くすれば、戦後の話ですよね。戦争が終わったときのあの頃の考え方に関して、もう完全に初心を忘れてしまった」
自筆の総譜(手書きのペンによる明晰な筆跡が読みやすい)を拝見したが、第9番や第10番の交響曲で用いられていた長田弘の言葉「幸福は何だと思うか」に基づくモチーフが、第11番でもトロンボーン、トランペット、そして最後にヴィオラのソロで語られている。それは私たちがいま繰り返し自問しなければならないテーマでもある。

今回のコンサートでは、若い頃の作品にもスポットが当たる。東京藝大学部卒業作品の「ピアノ協奏曲第1番」(1967)のソロを、今の若手でも最も注目すべき存在のひとり北村朋幹が弾くが、時代を超えて若い作曲家とピアニストがどう対決することになるのか、という聴き方もできそうだ。フランス語でタイトルや指示が書かれていることについて聞いてみると――。
「池内友次郎、矢代秋雄、三善晃の影響ですね(笑)。この頃だけですよ、こんなことをやったのは。その後はそういうことが嫌になってやめた。フランス語からは離れました。1960年代は前衛の時代と同時に、学生運動の時代です。そういう青春を送ってきたことと、今の仕事は、どこかでたぶん関わらざるを得ないと思う」
万葉集の恋の歌を題材とした「相聞Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」(1970年/2005年)はまとめて取り上げられ、長年にわたって深い信頼関係を築いてきた東京混声合唱団が歌う。そこには、日本語の言葉に対する愛着が脈打っている。
「日本人は言葉と共に生きてきたと思っているんです。『相聞』は万葉集からの曲ですが、その中に“孤悲(こひ)”という言葉がいくつも出てきてるんですよ。あの時代は万葉仮名でそう書いていた。“こひ(こい)”っていうのは、ひとり悲しむことで、成就した恋は本当の恋じゃない(笑)。そういう風な言葉遊びとか意味の裏側とか、元来日本人は好きなんですよね」
11作あるオペラからは第1作《死神》(1971/1978改作)からのアリア、第10作《高野聖》(2011)からのハイライトが古瀬まきを(ソプラノ)、中鉢聡(テノール)らにより演奏される。
「オペラとは演劇を伴った音楽か? それとも音楽を伴った演劇か? 僕の意見はいつも後者です。本質的には演劇だと考えたい。『ここは何秒あったらいい』とか『おそらくここは舞台装置ができたら何歩分ぐらい離れているだろうか?』とか、ストップウォッチを使ったりして、全部芝居を想像して書きます。オペラを作曲するのは演出と同じことです」
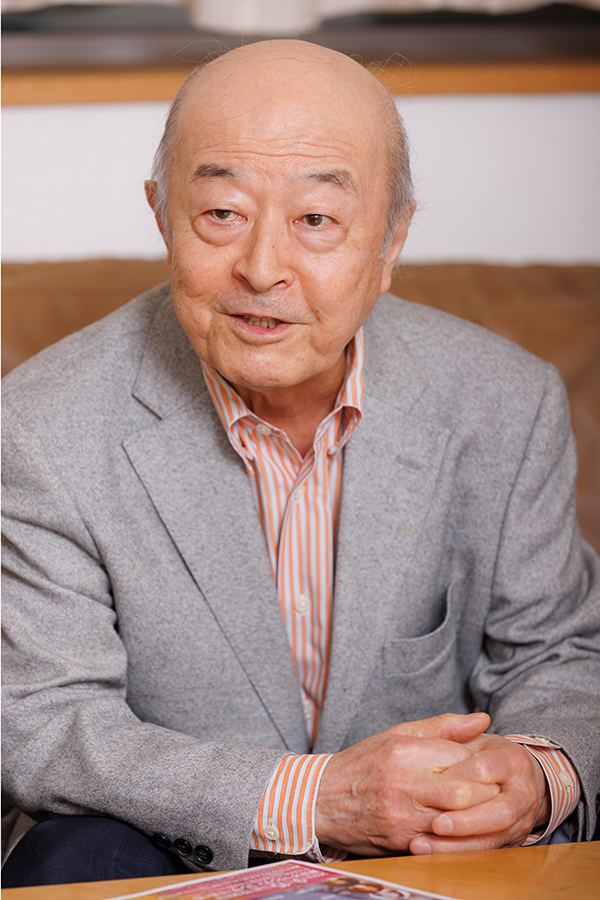
実はこの取材の後で、食事をご一緒することができたのだが、そのときに池辺さんはオペラの歌唱法について、その歌い方は演劇における俳優の歌のあり方をイメージしているのだ、と教えてくださった。それは、日本語のオペラにおける歌のあり方として、聴き手にとっても大きなヒントになるような考え方である。
今回の80歳バースデー・コンサートは、池辺晋一郎の作曲家人生の総決算とも言うべきプログラムになる。ぜひとも足を運びたい。
取材・文:林田直樹
(ぶらあぼ2023年9月号の拡大版)
【Profile】
作曲家。日本音楽コンクール、尾高賞などの受賞の他、映画・テレビ等の附帯音楽分野での受賞も多数。2004年紫綬褒章。18年文化功労者。22年旭日中綬章。作品は交響曲 No.1〜11、ピアノ協奏曲No.1〜3、オペラ《死神》《鹿鳴館》《高野聖》をはじめ管弦楽曲、室内楽曲、合唱曲など多数。演劇音楽は約500本を担当。現在、東京音楽大学名誉教授、東京オペラシティ文化財団ミュージック・ディレクター、石川県立音楽堂洋楽監督等を務める。1996年から13年間、NHK教育テレビ『N響アワー』の司会を担当した。
【Information】
池辺晋一郎 80歳バースデー・コンサート
2023.9/15(金)19:00 東京オペラシティ コンサートホール
出演/広上淳一(指揮)、古瀬まきを(ソプラノ)、中鉢 聡(テノール)、北村朋幹(ピアノ)、
東京混声合唱団、オーケストラ・アンサンブル金沢
曲目/池辺晋一郎:相聞 Ⅰ〜Ⅲ
《死神》から〈死神のアリア〉
《高野聖》からハイライト
ピアノ協奏曲Ⅰ(ピアノ協奏曲第1番)
シンフォニXI「影を深くする忘却」(交響曲第11番)(世界初演)
問:東京オペラシティチケットセンター03-5353-9999
https://www.operacity.jp
