文:青澤隆明

Aからの眺望 #20はこちら>>
Aからの眺望 #21はこちら>>
さて、ヴェンダースの新作『PERFECT DAYS』を観ながら、もうひとつ私が思っていたことのひとつは、今年の年明けに聴いた演奏会のことで、ずっと書きたいことがあった、ということだった。下野竜也が指揮をして、モーツァルトとブルックナーを巧みに組み合わせた、東京都交響楽団の定期公演のことである。
モーツァルトは人生の終わりのほうのピアノ協奏曲K.491、ブルックナーは始めのほうの交響曲第1番で、ともにハ短調を主調としたプログラムの全体構成が利いた。モーツァルトは1786年春の作で、ブルックナーは1866年に完成された初稿を四半世紀ほど経って改めた1890/91年ウィーン稿にもとづく演奏である。これがいずれもじんわりと胸に滲みる音楽となった。
モーツァルトのピアノ独奏は、津田裕也が終始ていねいに、心を籠めて弾き継いでいった。モーツァルトらしく変転する表情をきちんと描き出しはするのだが、それに翻弄されない、しっかりした芯というものも確実に保って手綱を手離さず、謙虚に弾き進めていく。ハ短調の劇性は強力なものだが、その運命的な力にも大きくは振り回されず、しかし自在な変化に溢れる心情をしたたかにみつめるまなざしが、モーツァルトの存在を愛おしく引き留めているように感じられた。
カデンツァは初めて聴くもので、津田裕也の自作のようだが、巧妙に構成されているうえに、モーツァルトの時代のピアノでは叶えることが難しいトリルを美しく活用していた。しかし華美に過ぎず、この人ならではの実直な端正さで、モダンピアノの円満な温かさを伸びやかに活かし、優美な時間を瑞々しく羽ばたかせていった。
そうして、第1楽章から第3楽章まで、劇性や抒情への深い耽溺ではなく、適度な距離を保ちながら曲を綿々と歩んでいくなかに、慎ましくも自ずと満ちてくる音楽の感興がある。それは、もしかすると天才の才気を超えて、まっすぐ私たちの胸に沁み入るものかもしれなかった。なぜなら、圧倒することや驚嘆させることでは、その余剰分のストレスが対象との距離や摩擦を生むからだ。そうした負荷がなく、ゆったりと構えて向き合えるだけ、私たちは自然体で無理なく聴くことができる。
津田裕也という実直な音楽家が、柔軟さもみせながら芯は頑固なままに、いかにひたむきに飾らず音楽に向き合う日々を実らせてきたのかがよくわかる演奏だった。下野竜也が誠心で応えるように都響を綿密に指揮し、簡潔な画布を織りなしていた。

そして、ブルックナーがやってくる。ジョナサン・ノットと東京交響楽団が昨年秋、こちらは荒っぽい初稿(リンツ稿ノヴァーク版)で野心作に臨み、ワイルドな、作者のいう“生意気”な性格を暴れ馬ふうに謳歌した演奏が忘れ難いが、下野竜也と都響のこのたびの演奏はオーケストレーションを拡充した改訂稿のほうを採って、難物の複雑さをじっくりと巧緻に描き出していった。矢部達哉をコンサートマスターとする都響が、作品と指揮の稠密な要求に応えるように着実に、しかも美しい響きをもって小節を積み上げていくのが輝かしい。
綿密な凝視による刻一刻の歩み、その細胞組織の積み上げが、大きな構築を織り成すように、まざまざと活力をもって結実していった。下野竜也という指揮者や、都響の演奏家たちが、長らく音楽する日々を重ねて、急がずに持ち堪えてきた着実な歩みが、まさにブルックナーの真意を射るようにこの演奏を実らせていたように思えた。作品世界への献身のうちに、音楽家たちの歳月の共鳴がしっかりと感じられた。それは決してファンタジーではなかった。一朝一夕に上がることなど、この世界にはなにひとつないのだった。
ハ短調がハ長調へと向かって行く流れが着実に積み上げられていったのは、それだけの下支えの質量が響きの細部にわたり充ちているからだ。ブルックナーの交響曲の終結は、モーツァルトの協奏曲がハ長調変奏の後にハ短調で結ばれるのとは好対照でもある。年明け早々、こうした作品と演奏家の確信に充ちた、幸福な対峙の時間を聴けたことに、実際大いに勇気づけられもしたのだ。
2024年は元日から災難続きで、都響のこの定期演奏会の幕開けもバッハのアリアの献奏から始まって、そこからハ短調の本篇に繋がれたのだった。ともかくも今年はハ長調に向かって頑張ろう——、とブルックナーの結びを踏み締めるうちに、私は素直に力強く思っていた。ハ長調というのがまた、私が偏愛するおかしな調であることも確かだとしても。
そのことを、『PERFECT DAYS』を観ながら、主人公の手仕事に重ね合わせるように、じんわりと思い出してもいたのだった。

そのようにして、ブルース・リウとのインタヴューをおえて、ラファウ・ブレハッチとアンドレイ・ボレイコ指揮ワルシャワ・フィルハーモニー交響楽団のコンサートの間に漂泊した『PERFECT DAYS』の時間を、私は淡々と、わりとずっしりと受けとめた。ゆっくりとシャンテを出て、夕方の地下鉄に乗ると、そこは馴染みの忙しげな日常の光景だった。
少しだけ長めに歩いて、サントリーホールに辿り着くと、視界に入らない場所から“Oh!” という声がしてきた。数時間前に話したブルース・リウがきていた。昨夜はソリストとして、彼らとショパンのヘ短調コンチェルトを鮮やかに聴かせていた。当夜はラファウ・ブレハッチがシューマンを弾く。
この日々のうちには起こりそうなものではあるが、私はまだ映画の時間を繰り延べるように歩いてきて、いきなり明るいコンサートホールのなかに入ったところなので、少しばかり驚いた。「さきほどは興味深い話をありがとう、音楽について、それから……」と言いかけると、「人生全体についてのことも話したね」とブルース・リウは言った。
ほどなくコンサートは始まった。昨晩とおなじルトスワフスキの小組曲が20世紀の響きで鳴り出した。映画も音楽も、私的な時間をしばらくの間、べつの時の流れに置くものである。私たちはその間、自分自身の生の流れをいったん譲渡するかにみせて、それぞれの作品の時間へと、心や感覚、思惟を重ねていく。
コンサートの場合には、知らない人々の間に分かち合われる拍手があり、自分の手もそこに重なり合っていく。匿名を束ねたその手の響きが、作品の時間をかっこに括るようにして、帰途の時間へのスイッチのような役割を担う。私は、私の未完の日々へとまた送り出される。
それからまた1週間ほど日々が経って、私はこれを書いている。あらかた書き終えたところで、映画にも感化されて、ひさしぶりにパティ・スミスの『HORSES』をかけた。十代のある時期、毎日のように聴いていたアルバムである。彼女の声が生意気に若い以上、私の心もそうあらざるを得ない。そうして、私はぼくになり、たちまちおれになり、わたしはワトゥーシを踊って、ほどなく“G-L-O-R-I-A”の燃え上がる文字と化していった……。
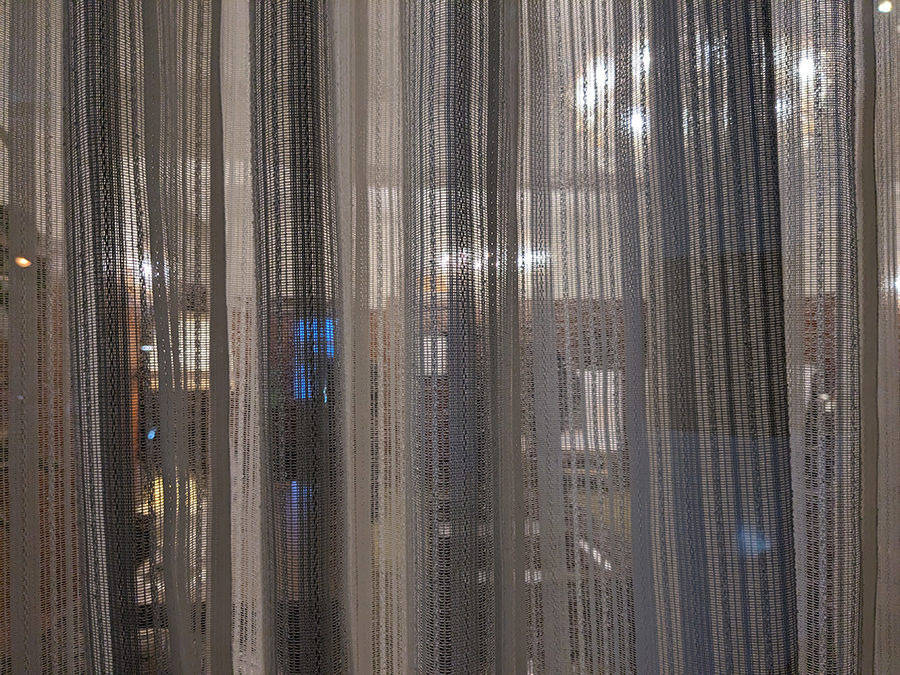
【Profile】
青澤隆明 あおさわ・たかあきら
音楽評論家。1970年東京生まれ、鎌倉に育つ。東京外国語大学英米語学科卒。主な著書に『現代のピアニスト30—アリアと変奏』(ちくま新書)、ヴァレリー・アファナシエフとの『ピアニストは語る』(講談社現代新書)、『ピアニストを生きる—清水和音の思想』(音楽之友社)。


