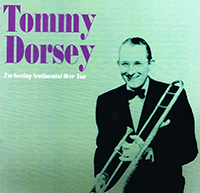text:藤本史昭
ところで、ジャズとクラシックは相反する音楽…そういう印象を持っている方は、実は少なくないのではないでしょうか。かくいう僕も、「その相反するものも、実はこんなにうまく混淆してますよ」ということを言いたいがためにこの連載を始めたわけで、つまりは自分の中にもそういう思いが潜在的にあるのかもしれません。
そのように考えてしまう最大の理由はやはり、クラシックが(基本的には)書かれた音を再現する音楽であるのに対し、ジャズは(基本的には)即興演奏を一義とする音楽、ということにあるのでしょう。しかしながら、即興演奏というのはなにもジャズの専売特許ではありません。むしろクラシックのほうにこそ、その伝統があったことは、このサイトをご覧の方ならよくご存知でしょう。バッハの、モーツァルトの、そしてベートーヴェンの即興演奏がいかに強力であったかは、どの音楽史書にも書かれていることです。

即興云々はともかくとしても、19世紀末から20世紀初頭にかけてのクラシックの作曲家たちは、ジャズやその先駆けとなったアメリカ音楽を視野に入れていたように思われます。ドビュッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチ…こういった人たちが、ジャズを想起させる作品を書いたことは、これまたみなさんご承知のことでしょう。
では、逆にジャズ側のクラシックに対する意識はどうだったか。
少なくとも、ジャズが鑑賞されるための芸術音楽となる前——年代でいうと1950年代以前は、クラシックを比較的近しいものと受け止めていたようです。そもそもジャズはその出自からして西洋音楽の影響を少なからず受けているわけで、たとえばジャズの前身ともいうべきラグタイムは、シンコペーションを多用したリズム・フィーリングこそジャズを思わせますが、あくまでも作曲された音を弾く音楽でした。
そしてなによりも、白人リーダーによるジャズ・バンドの台頭――これがジャズとクラシックを近しいものにしていた大きな要因ではないかと僕は考えます。白人ジャズマンの多くは当然のことながらクラシックの教育を受けていたし、その過程で多くのクラシック曲にも触れてきたはず。そんな中で、演奏時間が比較的短く、一般のリスナーにも馴染みのある、いわゆるライト・クラシックがレパートリーとして多く選ばれたのは、それほど不自然なことではないでしょう。
たとえば、トロンボーンのトミー・ドーシーが率いたバンドはクラシック曲のジャズ化が得意で、リスト「愛の夢」やメンデルスゾーン「春の歌」、ヨハン・シュトラウス「美しき青きドナウ」、ドヴォルザーク「ユーモレスク」などの録音を残しています。
クラリネットのアーティ・ショウはもっと本格的で(この人は早い時期からジャズとクラシックの融合=サード・ストリーム・ミュージックの先駆けみたいな活動をおこなっていました)、ラヴェル「ハバネラ形式の小品」、カバレフスキー「みじかいお話」、ドビュッシー「クラリネットとピアノのための小品」、プーランク「ワルツ」といったライト・クラシックどころではない曲をレコーディングしています(ただしこれらの演奏はジャズ・バンド用にアレンジされていこそすれ、原曲にかなり忠実なのでジャズとはいい難いところもありますが)。
そんな中、現代のジャズに直結する斬新なサウンドを響かせていたのが、クロード・ソーンヒルの楽団です。他の白人バンド・リーダーの例にもれず、ソーンヒルもまた徹底的にクラシックを学んだ人で、グレン・ミラーやベニー・グッドマンの許で腕を磨いたのち、1939年に自分のオーケストラを結成しました。
その音楽の特徴をひとことでいえば、クール。他楽団がとにかくスウィングしまくることに血道を上げているのを横目で見ながらソーンヒルは、フレンチ・ホルンやテューバというそれまでのジャズではあまり馴染みのなかった楽器を使い、夢幻的でスィートな演奏をきかせたのでした。
むろんこの人もまたクラシックに題材を取り、シューマン「トロイメライ」やチャイコフスキー「アラビアの踊り」、ムソルグスキー「古城」などの曲をジャズ・アダプトしているのですが、しかし彼の場合、そういう曲をやったことよりも、そのサウンド・テクスチャーにこそ、クラシックとの大きなつながりが見えるように思います。
そして、このソーンヒル楽団で編曲家として腕を振るったのがギル・エヴァンスです。ギルは後にマイルス・デイヴィスとの共演をはじめ、様々な仕事でのちのラージ・アンサンブル・ジャズに大きな影響を及ぼしていくことになるのですが、その話は次回くわしく。
[紹介アルバム]
ザ・リアル・バース・オブ・ザ・クール/クロード・ソーンヒル・オーケストラ・フィーチャリング・ギル・エヴァンス
ソーンヒル楽団におけるギルのアレンジ作品を集めたアルバム。クラシック曲ではチャイコフスキー「アラブの踊り」、ムソルグスキーの「古城」(アルバムでは「抒情詩人」というタイトル)を取り上げているが、特に後者は素晴らしく、これをきくと「展覧会の絵」全曲を編曲してほしかったとつくづく思う。現在はなぜか廃盤。復刻を切望する。
アイム・ゲッティング・センチメンタル・オーヴァー・ユー/トミー・ドーシー
トミー・ドーシー楽団が演奏したクラシック曲はいろいろな盤に散らばっているので、ここではこれを。ルービンシュタインの「ヘ調のメロディー」とリムスキー=コルサコフの「インドの歌」が収録されているが、よくもまあこれほどのスウィング・ナンバーに仕立て上げたものだと驚いてしまう。実にのどかなクラシック〜ジャズ・アダプト。
くるみ割り人形/デューク・エリントン・オーケストラ
白人ではないが、ジャズの父といわれるデューク・エリントンの本作も、クラシックのジャズ・アダプト作品の傑作として挙げられるべきもの。チャイコフスキーの原曲を尊重しつつも、まごうかたなきエリントンの世界を構築しているところに彼の、そしてその片腕だった編曲家、ビリー・ストレイホーンの天才を感じる。
ピアノ・スターツ・ヒア/アート・テイタム
白人でもビッグバンドでもないが、これはオマケ。ジャズ・ピアノの神様と呼ばれたアート・テイタムは、ドボルザークの「ユーモレスク」をよく取り上げていた。その神業的な指さばきは、ホロヴィッツやギーゼキングをも魅了したという。実際ホロヴィッツには、テイタムの十八番だった「二人でお茶を」を遊び弾きした映像も残っている。