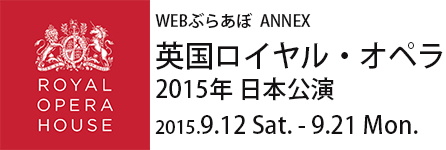(C)Sim Canetty Clarke
2010年英国ロイヤル・オペラ日本公演のころ、オペラの世界はネトレプコの《マノン》で盛り上がっていた。ベルリンでもニューヨークでもウィーンでも、大スターとなったネトレプコの、迫真のマノンに熱狂していた。次は東京の番だ! これで夢中にならないはずはない。ネトレプコは熱狂に値する魅力的なマノンだった。
だがネトレプコはひとりでマノンになってるわけじゃない。あの、サン・シュルピスでの誘惑場面を思い出すだけではっきりするはず。マノンがデ・グリューに歌いかけると、ヴァイオリンが、そしてオーケストラが、デ・グリューに働きかける。あの時のロイヤル・オペラのオーケストラは、なんとも官能的だった。
女が男を誘惑するとはこういうことだと、まずネトレプコがわかっていた。演出家もわかっていたはず。でも、最もよくわかり、実行したのは指揮者だったかもしれない。
あの時のアントニオ・パッパーノは、遠慮など無く、恥ずかし気もなかった。道徳を大切にする人にとっては、無慈悲というほかない。
そうだ、パッパーノって、こういう指揮者だったのだと、この指揮者を聞いた時を思い出してしまった。
いまならこの指揮者が現代有数のオペラの名手であるのは、よく知られている。だがパリで《ドン・カルロス》を指揮したころ、パッパーノはまだ名前が出てきたばかりだった。だが代1幕の、恋するようになった二人が引き裂かれる幕切れは、実に無慈悲だった。
ここで止めておこうなんて、まるで思わない指揮者なのかもしれません。教会だろうが人目があろうが、あとで困ったことになろうが、マノンはデ・グリューに迫る。神父デ・グリューが「愛している!」と叫び出すまで、その手を緩めない。マスネの《マノン》では、そこにマノンを歌うソプラノに負けないくらい、オーケストラを動かす指揮者の力が働いている。パッパーノはあの時、一線を越えていた。
いまはよくわかる。オペラ好きがどれほど強く、規範を乗り越えてしまう人物を求めているのかを。
オペラの舞台には一体どれだけの無作法者が登場するのだろう? カルメンにマノンにマクベス夫人、ドン・ジョヴァンニに、ボリス・ゴドゥノフにヤーゴと、いくらでも名が挙がる。その上、日常生活では絶対に近くにいて欲しくない人たちこそが、劇場で私たちを魅了する張本人なのだ。《ドン・ジョヴァンニ》がロマン派オペラを導いた星なのだとしたら、19世紀のオペラは不道徳な悪人に魅了されて始まったことになる。
ソプラノやバリトンは、役に扮するのだから必要かもしれないが、指揮者まで恥知らずになるまでもないだろう、という常識的な判断が、あまり常識的でないオペラという芸術においては、まちがっているのだと、パッパーノは改めて教えてくれた。
コンサートの指揮者としてのパッパーノもすばらしいと、このあいだのローマ・サンタ・チェチーリア国立管弦楽団とのコンサートを聴けば思う。でも、演奏されたロッシーニの序曲を聴くと、その向こうに愉快な男女のうごめく様子がうかがえる。ついオペラ指揮者パッパーノを想像してしまうというもの。あの、艶っぽいマノンを、これでもかとばかり不道徳に、そしてあでやかにしてしまったロイヤル・オペラの音楽監督だ。
ロイヤル・オペラが今度の日本公演で上演するのが《マクベス》と《ドン・ジョヴァンニ》というのは、音楽監督に合わせたからなのかもしれない。どちらも筋金入りの不道徳な悪人のオペラなのだ。断言できる。舞台では罪作りな所業が行われる。前もって言ってしまおう。気をつけなくてはならないのはアントニオ・パッパーノだ。
(文:堀内 修 音楽評論家)