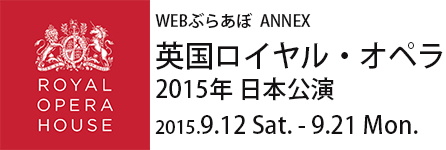Photo:Nick Heavican
ディドナート いつも多いです。ケルビーノ(《フィガロの結婚》)、ドラベッラ(《コシ・ファン・トゥッテ》)、セスト(《皇帝ティートの慈悲》)、そして複雑で音楽的にもむずかしい大役のエルヴィーラね。バロックやイタリア的なベルカントもずっとやってきたし、一つの方向にのみ力を入れるということはありません。
―― ロッシーニでもロジーナとエレーナ(《湖上の美人》)では全く違うのに、どの役も観客を信じさせます。特別な演技の訓練でも?
ディドナート 観客が私の役の感情や行動に没頭してくれることがゴールなのです。音楽的、声楽的要素と演劇的要素が相互作用することによって歌うことが楽になり、演技も滑らかになります。ズボン役でもプリンセスでも闘士の役でも、観客が役の中に引き込まれてほしい。正式な演技指導を受けたことはありませんが、演出家にすべてを頼ってニュアンスや真実を伝えるよう心がけています。
―― 数年前にロイヤル・オペラの《セヴィリアの理髪師》で、車椅子で歌っていらしたのを拝見しました。すごい迫力でした。
ディドナート これも同じことです。綿密なリハーサルを重ねているし、出演者のみんながこのオペラを熟知しているからお互いへの信頼も厚く、即興も多かったです。思えばロジーナが怪我をして車椅子に乗っているシチュエーションだってありうるでしょ。すばらしい思い出になったわ(笑)。
―― ほんとうにあの舞台は今や伝説ですね。ところで慣れているオペラでもいやな演出に出会ったらどうします?
ディドナート もし明らかな間違いがあったり誇張が過ぎたり、いかがわしいことを演出家から要求されたら、その理由や動機をききます。肉体的に意味のないことはできません。理解するまで質問攻めにしますが、これも仕事ね。
―― あなたにとってロイヤル・オペラハウスはどんなところですか。
ディドナート 2003年に《利口な女狐の物語》でデビューして以来、いつでも帰って来られる私のキャリアの中心部です。バービカン・ホールやウィグモア・ホールも含めて、ロンドンは両手を広げて私の情熱を受け止めてくれます。
―― マエストロ・パッパーノはどんな人?
ディドナート 特別な人。特別なピアニストであり指揮者であり、人間的にも特別です。(声を震わせて)彼からは音楽や情熱が溢れ出てくるの。同時に皆にベストを要求し、一緒に音楽を輝かせてくれます。でもコラボレーターとして、決して安全な場所を提供してくれるわけではありません。彼にとって重要なのは音楽体験と演劇体験を後で貼り付けるのではなく、舞台とオーケストラを最初から一つの物として作り上げることなのです。
(インタビュー・文 秋島百合子 ロンドン在住ジャーナリスト)