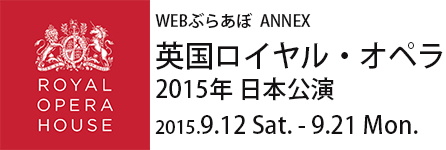カスパー・ホルテン
ホルテン:
だいぶ前ですが、1999年にデンマーク王立歌劇場で初めて演出しました。また、2012年には『JUAN』というタイトルで、《ドン・ジョヴァンニ》の映画も発表しました。それを含めれば、今回の演出が三度目になります。以前演出したオペラを新しく手がける場合、難しく感じる作品もありますが、《ドン・ジョヴァンニ》の場合は三度ともまったく違ったアプローチで取り組むことができました。映画の場合は自然主義的な手法が必要ですが、今回の舞台演出では、大部分が主人公のイマジネーションの中で起こるという、いわばヴァーチャルな世界を扱っています。

映画『DON GIOVANNI(Juan) 』の場面
(ロイヤル・オペラ プログラム誌より)
ホルテン:
だれもが自分なりのドン・ジョヴァンニ像を持っているとは思いますが、私の考えでは、彼はきわめて豊かなイマジネーションの持ち主で、女性と知り合うと彼女が心の中で望んでいること、夢や欲望を読み取ることができ、一瞬だけその夢をかなえてあげることができるのです。その意味では彼は芸術家肌だといえるでしょう。でもそれは幻想であり、女性たちはそれに気づかず、彼が創り出した世界を信じてしまい、あとで傷つくのです。誰も本当のドン・ジョヴァンニに会うことはないのです。こうした世界を描くには、プロジェクション・マッピングを用いるのがぴったりではないかと、舞台美術のエス・デヴリンと構想を練っている時に考えつきました。舞台上の建物は、いってみればドン・ジョヴァンニ自身であり、彼の頭の中の象徴でもあります。そこに彼が創り出す夢や幻想--そして彼が付き合った多くの女性たちの名前--をプロジェクションで映し出し、しかもそれらがいかに儚いものであるかも示しています。最終的にはすべてが消え去り、彼は独り取り残されるのです。

リハーサル中のカスパー・ホルテン(ロイヤル・オペラ プログラム誌より)
©ROH_Bill Cooper,2014
ホルテン:
ドン・ジョヴァンニのような人物にとって、究極の罰とはなんだろうかと考えた時に、それは孤独なのではないでしょうか? 結局、彼は孤独になることが怖いから、次々と女性を誘惑しては、その瞬間だけ現実を忘れようとするのです。その意味で、彼にとっての「地獄落ち」は独りになることなのではないかとこの演出では考えます。(インタビュー・文 後藤菜穂子 在ロンドン、音楽ジャーナリスト)
*インタビューは(2)に続きます。