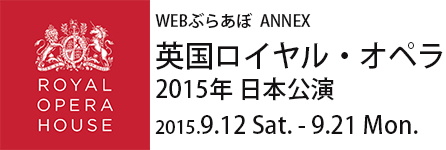「僕のオーケストラを下のあそこから上のここ(オーケストラ・ピットから舞台上)へ持ってくることが長い間の夢でした」
5月4日、オペラ・ハウスでは見慣れない音響パネルに囲まれたステージで、ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団(ROH楽団)を背にアントニオ・パッパーノがそういうと、まだ一音も発していないのに観客は大喜びして大拍手を贈った。通常のホールの2倍はある客席はぎっしり詰まり、いつもと違う音楽を期待してただならぬ熱気に溢れていた。後日批評家陣は、諸手を挙げて絶賛評を贈った。

Photo:ROH/ Sim Canetty-Clarke
前半はフランス音楽で、ラヴェルのピアノ曲「鏡」から管弦楽に編曲された第3曲「海原の小舟」と第4曲「道化師の朝の歌」で始まった。光の中で揺れ動くような弦楽や木管が牧歌的に響き渡り、「道化師」は鋭くリズミカル、両方の曲に潜む暗さも含めて印象派的な情景を呼び起こした。続くエルネスト・ショーソンの「愛と海の詩」はアンナ・カテリーナ・アントナッチの劇的な独唱で、初恋(水の花)と愛の終わり(愛の死)を語る。アントナッチは、ロイヤル・オペラでは特に《トロイ人》のカッサンドラが衝撃的だった。さらに2つの曲の間に間奏曲があるので、オーケストラの聴かせどころも十分含まれている。ゆったりと、けだるいほどの愛の言葉を支えた演奏は情熱的だった。

Photo:ROH/ Sim Canetty-Clarke
後半は打って変わってバーンスタインのバレエ音楽「ファンシー・フリー」だ。軽やかなリズムの中にジェローム・ロビンスのステップが浮き上がり、観客は親密なバーかクラブにでもいるように“バンドリーダー”、パッパーノのスイングに酔いしれてしまった。ROH管弦楽団がバレエのオーケストラであることもしっかり示してくれたのである。
最後はスクリャービンの「法悦の詩」。光が差すように空間を貫くトランペット、大きく包み込むホルン等の金管楽器がゴージャスに鳴り響き、恍惚の竜巻に吹き上げられて天に達するような心地になった。
(秋島百合子 ロンドン在住ジャーナリスト)