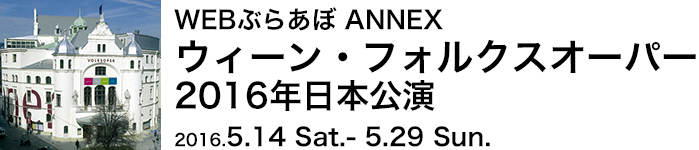フォルクスオーパーでの《メリー・ウィドウ》が、初のオペレッタ演出となったマルコ・アルトゥーロ・マレッリ。初演当時に語られた演出コンセプトや作品への視点を、3回にわたってご紹介していきます。

演出家、マルコ・アルトゥーロ・マレッリ
「今(タイムリミットの)0時5分前。小国は破産寸前で、救済保護策も無い状態」
今回初めてオペレッタを演出するマルコ・アルトゥーロ・ マレッリは、《メリー・ウィドウ》が始まるときのシチュエーションをこのように描写している。これは、「きわめて深い精神的痛手を負った2人の人間が、幸せを求める道筋において、お金の存在が愛を困難にするという冷徹な事実を繰り返し認識させられる」(マレッリ)物語なのだ。
しかしフランツ・レハールの古典的作品の新演出は、優雅さと人間の真情を表しながらも、なお手堅い喜劇的作品なのである。
真面目であることとユーモアは、必ずしも相反するわけではない。それどころか、往々にして両者はまさに互いに欠くべからざる存在なのである。そのようにして、マレッリは、新演出が聴衆との融和的盟約ではないことを、熱意を込めて表明した。
「劇中の当事者たちは、自分たちの置かれた状況と真剣に取り組まなければなりません。かれらが、物事の全体を喜劇的にも感じていることを表現するのではありません。可笑しさというのは、感じ方の食い違いから生じるものなのです。わたしがものすごく真面目に考えているとき、観客はわたしのその滑稽な部分に気づくのです」

国の一大事に公使ツェータは策をめぐらす
Photo:Dimo Dimov / Barbara Palffy / Volksoper Wien
ともかく小国ポンテヴェドロの状況は、「きわめて深刻」である。国は破産寸前、未亡人ハンナ・グラヴァリがポンテヴェドロ人と再婚することによってもたらされる何百万にものぼる財産によってのみ救われるのである(「現在の金額では…」マレッリによれば、“何十億に相当する”)。しかし国が破産してしまうと、パリにある公使館も閉鎖されることになる。「豪勢で愉快な暮らしともおさらばして、荷造りしてわびしい田舎に帰らなければならないのだろうか? パリで心地良い生活をしていたポンテヴェドロの面々には想像を絶すること!」だった。まだ一度もポンテヴェドロに行ったことのないヴァランシェンヌもしかり(ツェータとはパリで知り合い結婚した)、彼女は「生活基盤が脅かされるストレス”の真っただ中にあって、パリの貴族カミーユ・ド・ロションの魅力に圧倒されそう」なのである。
しかし、断然誘惑になびきそうな元グリセット(=薄給労働者)の「品行方正さ」は、自分の潜在的恋人がまず他の女の夫になることを要求する。「カミーユとヴァランシェンヌは、エロティックな欲望をそれらしく見せかけるのではなく、真に体験しなければなりません。これはお遊びではなく、危険な行為なのであり、この婦人にとって本物の危機、永遠の火遊びなのです」
すでに初演の時代、《メリー・ウィドウ》のオペレッタを観て誰でもが笑えたわけではなかった。モンテネグロの政治的な代表者は、自国と自国のトップクラスの代表者がレハール、(台本作者の)レオンおよびシュタインの架空の国“ポンテヴェドロ”に対するカチカチの風刺によって笑いものにされることに我慢できなかった。
ここでは公使ツェータに体現される国は、国の好ましからざる経済的・政治的状況を、婚姻政策によって解決することを求めていた。しかしここでツェータは、最初は互いに激しく反目し合っていた理想的なカップル、ハンナ・グラヴァリとダニロの気持ちを考えずに強引に事を運んだのである。
[次回に続く]
*チケットのお申込みはこちら
NBS公式サイト
http://volksoper2016.jp